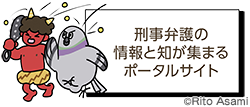—— 刑務所(刑事施設)は犯罪者が収容されているということで、刑務所に対する一般の人のイメージは悪いし、むしろ日本社会には、そういう犯罪者は社会から隔離して、排除する意識がまだ根強く残っていると思います。国は受刑者の社会復帰促進、再犯防止の施策を進めています。そこで、今日は、美祢社会復帰促進センターや府中刑務所長などを務められた手塚さんに、刑務所の現状や受刑者の社会復帰についてお話しいただきます。
1 刑務官という仕事
—— はじめに、手塚さんは、刑務所の仕事を始めようということになったきっかけはどんなことでしょうか。
手塚 私は、最初、刑務官になるつもりはありませんでした。私の父が刑務官で、その影響が非常に大きかったと思……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2020年05月27日公開)