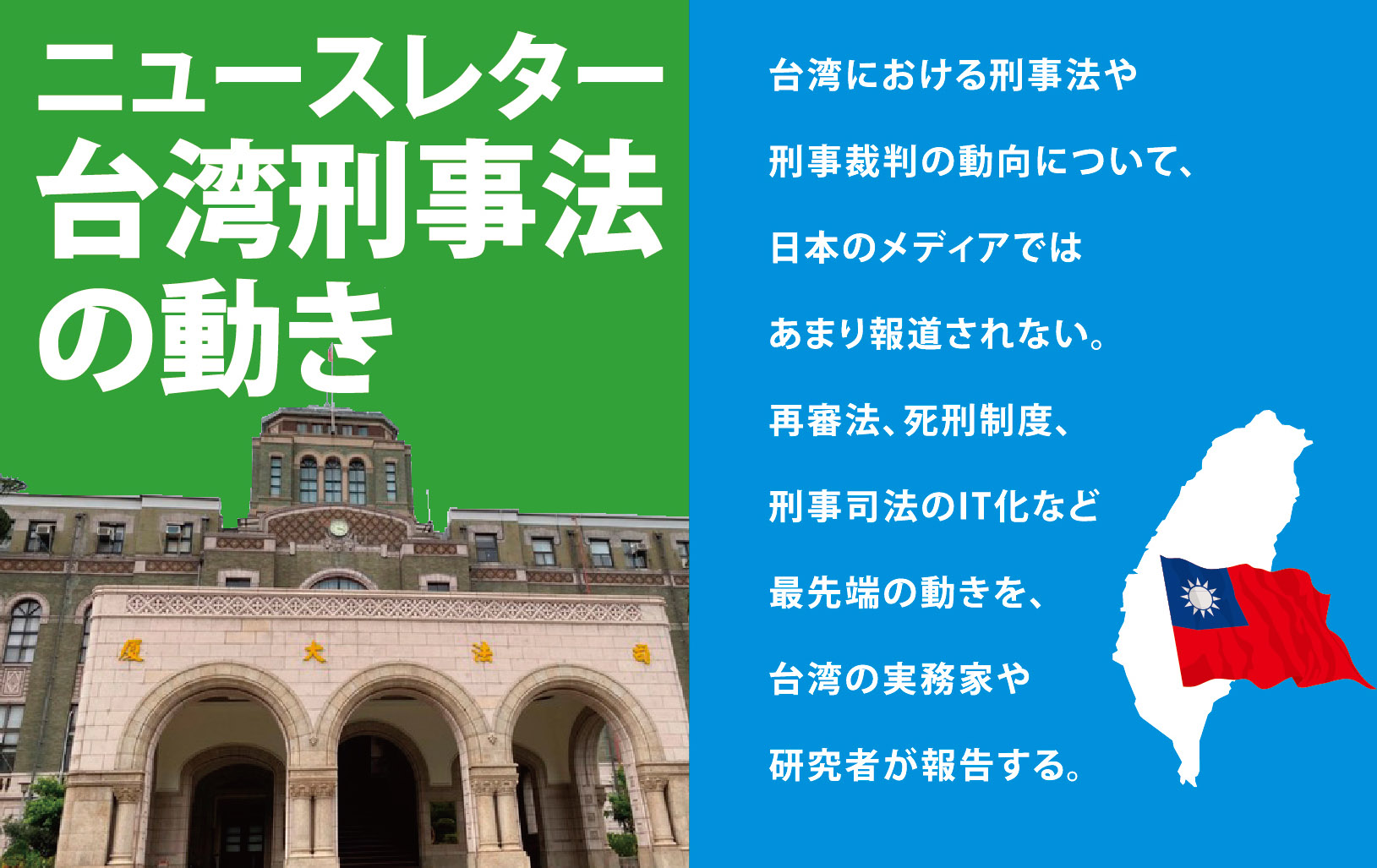死刑が確定した死刑囚37人((憲判8を言い渡した後、台湾の司法実務においては、憲判8の趣旨に基づき死刑を言い渡した事例が既に現れているが、いずれも上訴審に係属中であり、新たな死刑事件が確定したことがない。一方、憲判8において憲法訴訟を提起した37人の死刑囚のうち、黄麟凱は2025年1月に銃殺による死刑が執行された。その結果、現時点で確定死刑囚の人数は36人となっている。これら36人の死刑囚はいずれも、憲判8の見解に基づき、検察総長により最高裁判所に非常上告の申立ての途を通じて救済を求めている。))が、死刑制度は憲法に違反することを理由として憲法審査を提起した。これに対して、台湾の憲法法廷(憲法裁判所に相当)は、2024年9月20日に、画期的な113年憲判字第8号判決(以下「憲判8」)を言い渡した。
本事件では、口頭弁論から5カ月をかけて審理を行い、死刑制度が憲法違反か否か、その適用条件が中華民国憲法に適合しているか、現行の手続が法的に適正手続の要求に合致するかといった重要な憲法問題に焦点が当てられた。憲判8が出た後も、憲法法廷は全面的に死刑廃止の立場を採用していないが、死刑の適用範囲および手続保障の観点から多くの制限を加え、台湾の人権の発展と刑事司法制度に重要かつ広い影響を与えた。
1 申立ての背景と裁判所の審査の焦点
本件では、死刑判決が確定した37人の元被告人が、現行死刑制度は、憲法が保障する生命権と訴訟権((中華民国憲法第16条の規定によれば、人民は請願、行政訴願および訴訟の権利を有する。そのうち「訴訟権」とは、人民が自己の権利を侵害された場合に、法律に基づき裁判所に対して迅速かつ公正な審判を請求する権利を意味する。その内容には、聴聞権、公正な手続保障、公開審理請求権および手続的平等権などが含まれる(司法院大法官解釈第482号参照)。
憲判8における死刑問題の文脈において、この訴訟権はとりわけ、死刑事件の被告人が捜査段階から審理段階までの各過程において、防御権を実効的に行使できるよう確保されるべきことを意味する。具体的には、憲判8が指摘するように、死刑事件の審理においては、被告人に弁護人の援助を付与し、その防御権の行使を確保すべきである。また、訴訟権を保障するため、死刑事件が第三審に上訴された場合には、口頭弁論手続を実施すべきである。))に違反すると主張し、本件申立てをした。
違憲主張の対象とされた点は、以下の3項目である。すなわち、①刑法33条の死刑を主刑とする規定の合憲性、②死刑が適用される犯罪の種類の合憲性、③刑事訴訟法の第三審(上告に相当)の審理および裁判手続の合憲性である。憲法法廷は、2024年4月23日に公開法廷で口頭弁論を開き、多くの専門家と学者を招き、3つの審査上の要点──「死刑制度は本質的に違憲か否か」「死刑の適用条件は違憲か否か」「死刑案件の現行審理及び裁判手続は合憲か否か」──を設定した。死刑制度が本質的に違憲か否かは、国民の大きな関心事だったが、法廷はこの核心的な問題を回避し、一部の法条および実務運用の合憲性を審査し、限定解釈をするに留まった。死刑制度そのものが憲法の趣旨に合致しているか否かについての明確な判断は行われなかった。

2 判決の主文と要旨
⑴ 死刑制度は絶対の違憲ではないが、極端な例外状況でのみ適用可能
憲法法廷は、死刑について国家が個人の生命権を最も厳しく剝奪するものだとしつつ、現行憲法秩序と国際人権基準の影響下では、必ずしも違憲ではないと説示した。ただし、死刑は「犯罪の情状が最も重大」である事件に限定され、「最も厳格な法的手続」の要件を満たす場合のみ合憲とされることも示した。
これにより、死刑は一般的な刑罰ではなく、手続が完備され、特別な情状が認められるという、十分な法的理由充分な法理に基づく場合に限り適用されるべきとされた。
⑵ 刑法旧348条1項(1999年改正)の一部規定違憲
刑法旧348条1項により、強盜殺人罪の法定刑は唯一死刑のみが規定されていた。憲法法廷は、このような法定刑の定め方による場合には、裁判官が具体的情状により刑の相当性を審査することができず、罪刑均衡や比例原則に違反する点で違憲だと判断した。ただし、台湾では、憲法法廷は抽象的違憲審査を行い、個別の事件については最高裁判所が審理することになっているため、憲法法廷は刑法旧348条1項が適用された本件の原因となる事件について、検察総長(検事総長に相当)により最高裁判所に非常上告をするものと判断した。
⑶ 憲法による手続保障の要求:最も厳格な手続原則
適正手続を保障するため、憲法法廷は、死刑を適用するときに必要な手続保障として、以下の具体的な事項を要求した:
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年10月16日公開)