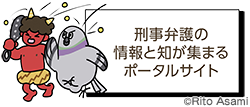来いというから行く!
私が裁判員を経験した翌年の2011年秋に、縁あって弘前大学(青森県弘前市)で開催された「裁判員裁判シンポジウム」に招かれた。それ以来、同大学には度々招かれている。
その後、2014年に「死刑執行停止の要請書」を提出したのだが、その際に遠く青森から賛同署名の手を挙げてくれたのが小野利(おの・かつ)さんだ。しかも、職場の同僚でやはり裁判員経験者の方にも声をかけてくれて、2筆もの署名をもらうことができ、青森まで日帰りで行った甲斐があった。彼女の本業は介護施設に勤務する介護職だが、多岐にわたる側面の顔のほうが色濃い。
まずは生活を成り立たせるために、お給料もらっているのは介護職。施設に勤務して25年くらい。在宅や施設など様々な形の介護。ご家族の方がいなくて、誰かの手を借りなければならない方々とご縁をもった私にできることとして、したくてやってきました。
お茶やお花の世界は若い頃からずっと。うちの姑がお茶やってて、道具とか無駄にならないようにって、ただ着付けとかもあくまでお稽古事でした。それを資格取った段階で、活かしていこうと施設のお誕生会なんかで、利用者さんに着物を着せてお茶会やって楽しんでもらっています。腰が曲がっている人が着物を着て口紅つけたら、すっごくいいお顔をしてシャキッとする。そうすると、ご家族がとっても喜ぶの!
小野さんは、「利園(りえん)」という雅号を持っている。これは、煎茶道の免状の証である。むろん、それだけではない。もはや趣味の領域を超えている。
お茶やお花は学生時代から、お琴とかピアノもやってたんだけど、ピアノは3日でやめました(笑)。華道、煎茶道、抹茶道、着付けが残っている感じ。でも、これを商売にする気持ちはないんです。なぜかというと、実家の婆さんたちの着物とかを寝かせておくのはもったいないし、姑なんかは教員でしたけど、自分の退職金を全部お茶道具や着物に変えるくらい楽しんだ人なので、そういうのを利用して皆さんに楽しんでもらえればということ。子どもにも無料で教えていて、やりがいありますよ。
そんな多才な小野さんが裁判員を務めたのは、2012年のことだが、公私ともに多忙を極める日々ゆえだろうか、その記憶は曖昧である。しかし、あえてわからない部分はそのままに、もっと大切な部分に迫るべくお話を聴かせてもらった。なお、事実として重要な部分については、弘前大学人文社会科学部、平野潔教授に資料提供をしていただいた。
裁判員制度ができた当時、報道で見聞きはしていたが、懐疑的に捉えていたそうだ。
関心なんて全然ない。裁判物のドラマなんかもあまり興味なかったな。素人が裁判員なんかできるのかなって思ってましたね。やっぱし裁判ていうのは、ちゃんとした頭のいい人(裁判官)がやるべきものという考えでしたね。まさか自分がやるとは思ってもなかったし。
結果論だが、小野さんはきちんと裁判員を務め上げている。それに、冒頭のとおり同僚に裁判員経験者がいる。
たしか、最初の年に候補者登録通知を受け取っていたみたい。私より1年か2年早くやっているのよ。でも、私が(候補者登録)通知を受け取った時は、そのことを知らなかった。後で話してて「そうだったの?」って。何をきっかけに話したのかは記憶にないんですけど。
うちの主人が裁判官に興味があったんですよね。「能力と金があれば学校に行って、自分は裁判官になりたかった」って言ってるんですよ(笑)。で、それ(候補者登録通知)を見て、「裁判員(候補者)に選ばれたんだから」って、どれどれっていう感じで主人が先に(封を)開けましたね。羨ましがってた(笑)。
裁判官になりたかった人にとって、裁判員は疑似体験する最良の機会と言える。その時点でも、「ピンとこなかった」という小野さんだが、翌2012年の初夏に呼出状を受け取ることになる。
やりたい、やりたくないの次元よりも、来たんだから行かなきゃいけない。でも、受け取った記憶はない(笑)。私が行って、何かできることがあるんならっていう、いつもそんな感じで、なんとかなるって(笑)。
その時は、(職場の)部長に言ったのかな? そうしたら部長がすぐに会長のところに話して、「それはもう行かなきゃダメだ。ちゃんと行きなさい!」って(笑)。シフトを代わってもらって、公務休暇(有償)。
その代わり私も、普段から「ここ頑張って出てくれる?」って言われたら、二つ返事で「わかりました!」って。いつも自分が精一杯やれることはやりたいと思っている。仕事ができない部分とかがあれば、それはみんなから助けてもらっているし、だから自然にやっていることなの。
勤務先は個人事業主らしいが、比較的制度初期の段階において有償での公務休暇とは素晴らしい対応だと思う。裁判員になった従業員がいたという前例があったことも大きいだろう。そして、小野さんの互助の精神は東北地方だからというわけではなさそうだ。
「来いと言われれば行くだけ」と選任手続日の朝、小野さんは自動車で約1時間かけて青森地裁へと向かった。むろん初めての裁判所である。


驚くより残念——選任手続~初公判
県庁はね、行ったことがあったけどその並びに(裁判所が)あるのを初めて知ったかも。中は暗かったな(笑)。血を見るような事件は嫌だったかもしれない。でも、「アナタはこれをやってください」と言われたら、「はい。わかりました」だね。自分に与えられたものっていう考え方。何事もそうしてきたし。
よくうちの爺ちゃん、婆ちゃんから「大変とか、あぁ疲れたとか、そういう言葉は心の中で思っても、人前では言うもんじゃないよ」って言われてきたから、なんだろ? なんて言えばいいんだろう……。
やはり、育ってきた環境だろうか、嫌かどうか以前に断るという選択肢やそういう感性そのものがないように感じる。もはや人格としての価値観と言えるだろう。その姿勢は、選任手続の際も大いに現れる。
家出る時に、主人から「もし事件(裁判)が終わって、後で逆恨みされたりしたらどうする?」って言われたけど、そんなことあるのかしら(笑)。(候補者控室には)何百人じゃないか、何十人だったかな……。そこに行っているということは、なんか当たり前に選ばれるような感覚で、そんな気持ちでいたかもしれない。
あまり記憶にないけど、(発表方法は)電光掲示板だったみたい(笑)。選ばれて、困ったとかそういうのよりも、そうなんだ、じゃあやらなきゃいけないんだって。そんな全然難しく考えてないよ(笑)。
「当たり前に選ばれる」、この感覚は一定数の裁判員経験者から聞くことがある。いずれにしても、裁判員に選任された。朧気な記憶を振り絞って思い出してもらった結果、60代の男性3名に40代、50代の女性3名、補充裁判員が男女1名ずつというやや年齢層の高い合議体だ。そこに男性3名の裁判官を加えた全員で初日の昼食会が開かれた。
どこから来た誰々って自己紹介してましたね。あれ? 番号で呼んでいたかもしれない。裁判長はひょろっとした人だった(笑)。「選ばれましたね」って言ってました。そういえば、裁判終わった後に、法服着て法廷で記念撮影もしてたかな?
3日間お弁当だったけど、2日目にはみんなして漬物持ってきたり、おやつ持っていったりして食べてたね。こっち(の地域)の漬物だよとか、こっちのお菓子だよって持ってきてた。自然にそれぞれ「これ食べて」って出してたよ。裁判所からもおやつ出た出た。チョコレートとかお煎餅とかあったよ。テーブルの上にたくさん並んでたね。
小野さんによると、人が集まる際に食べ物を持ち寄るのは青森(東北地方)の文化だそうだ。それに、一番よく話したという女性の裁判員は、本州最北端である下北半島から来ていたそうだ。青森県といっても広い。食文化一つとってもだいぶ違うはずだ。
事件は、祖母と同居する母子家庭の息子(当時22歳)が自宅寝室に灯油を撒き、マッチで着火し家屋を全焼させた現住建造物等放火である。隣接する小屋の一部も焼損したが、幸いにも誰もケガを負うことなく鎮火した。
公訴事実に争いはなく量刑のみを判断する裁判だったため、選任手続日の午後から初公判の裁判は、3日後には判決公判を迎える正味2日半の期日で組まれていた。自身も息子を持つ小野さんにとって、他人事とは思えない事件の裁判が幕を開ける。
舞台(法壇)があって、客席(傍聴席)があって、テレビやお芝居の世界みたいな気がしたね。満席ではないけど、空席はそんなになかったな。緊張? するもんかな?
通路がどうのこうのって、(退廷するときは)被告人が先に出て、私たちが後から出るという感じだった。被告人は、Tシャツにサンダルでいて、私またちゃんと背広でも着てネクタイでもして来るものだと思ってたの。そんな格好でもいいものなんだって気がした。哀れだったな……。なんでこんなことしたのかなっていうぐらい、申し訳ないという表情に見えたね。
ニュースで(事件報道は)見てたけど、やっぱし何か間違いというか、こういうことはあり得るんだなって思ったもん。驚くというか残念が先だねぇ。
青森地裁は立派だが、法廷によっては被告人と裁判員たちが通る通路を共有していることもあるだろう。そして、注目の冒頭陳述といきたいところだが、小野さんにとっては霞んだ記憶のようだ。

検察官と弁護人、どっちがどっちかというのも記憶にございません(笑)。書類とかもありましたけど、わかりませんでした。知識がある人はわかったでしょうに、私の場合は理解とかでなく、その場にいるだけ(笑)。とにかく、被告人に対しての気持ちはいろいろあったけど、淡々と時間が過ぎていった感じだったな。
事案からして、現場の写真や見取り図、あるいは灯油缶やマッチなどといった証拠類があるはずだが、「記憶にございません」とのことだ。他方で、被告人質問においては、小野さん自身も積極的に手を挙げ、事件の背景といえる部分が浮かび上がってきた。
(2025年11月14日公開)