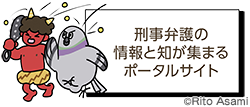はじめに
——本論に入る前に、村木厚子さんの職歴を簡単に教えていただけますか。
村木 1955年に高知で生まれて、大学まで高知にずっといました。就職で東京に来て、当時の労働省に入省、その後、厚生省と労働省が一緒になり、2015年まで勤務、都合、37年半、公務員をやっていました。それだけなので、履歴書が非常にシンプルなんです。厚生労働省を辞めて3年たって、今は、伊藤忠商事の社外取締役など企業の仕事と、津田塾大学総合政策学部で学生を教える仕事をやっています。 大学では、2つ講座を持っていて、1つは、社会保障や労働政策の基礎講座で、もう1つは、総合政策学部が社会課題の解決にチャレンジする人材を育てるという目的なので、自分の人的なつながりの中で社会課題にチャレンジしている人たちをたくさん呼んできて、学生たちに興味の幅を広げてもらう講座です。日本の少子高齢化とか、子どもの貧困など厚生労働省で私自身がやってきた分野は、私が授業をしています。1年生の最初の授業なんです。1 郵政不正事件で考えたこと
郵政不正事件での逮捕・勾留
——村木さんは、郵政不正事件((2009年に、大阪地検特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体、厚生労働省、ダイレクトメール発行会社、広告代理店、郵便事業会社等の関係者を……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2018年09月24日公開)