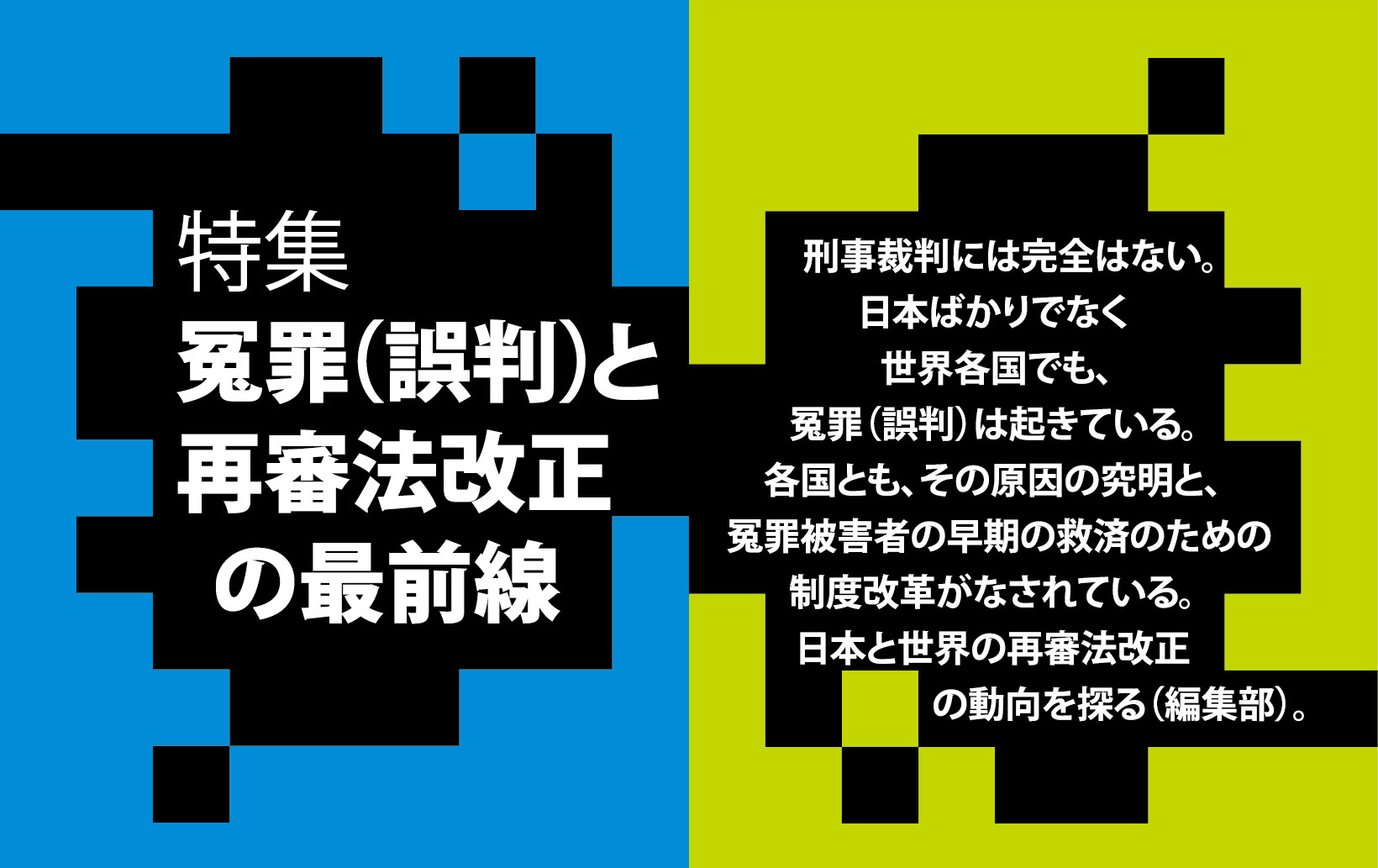【12 再審請求審において取り調べられた証拠の再審公判における取扱い】(20分)
この論点については、鴨志田から日弁連案451条の2の趣旨及び立法事実について、以下のとおり説明した。
・日弁連案は、再審請求審において取り調べられた証拠は、再審公判において当事者が異議を述べない限り当然に取り調べるべきであり、その限度で伝聞法則の適用を除外するが、証明力を争う機会を保障すると規定する。
・6号再審では、再審請求審でも実質的に有罪認定の吟味を行うので、有罪無罪の判断と重なる。本格的な再審事件では、再審請求手続が重厚化しており、検察官も関与している。にもかかわらず、再審公判で改めて取調べを行う必要があるとなると、請求人にとって過重な負担となる。
・袴田事件では、再審請求審で9年間にわたり主張立証が行われ、差戻後の即時抗告審だけでも2年3か月にわたって「5点の衣類」について審理が行われた。にもかかわらず、再審公判でも改めて有罪立証が行われたので、再審公判だけで1年7か月の期間を要した。再審開始決定に対する不服申立てが審理の長期化の原因であるが、さらなる長期化を食い止めるため、再審請求審で検察官が関与して取り調べたものは、再審公判でも当然に証拠とすべきである。
・徳島ラジオ商事件でも、検察官は、再審請求審で検察官の反対尋問を経た証人尋問調書等についても証人尋問の実施を求めたため、数年単位の審理が必要となる事態も想定された。裁判所は、証拠物として取り調べるとか、刑訴法328条で採用するという方法で事態を打開したが、証人尋問調書は証拠……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年10月29日公開)