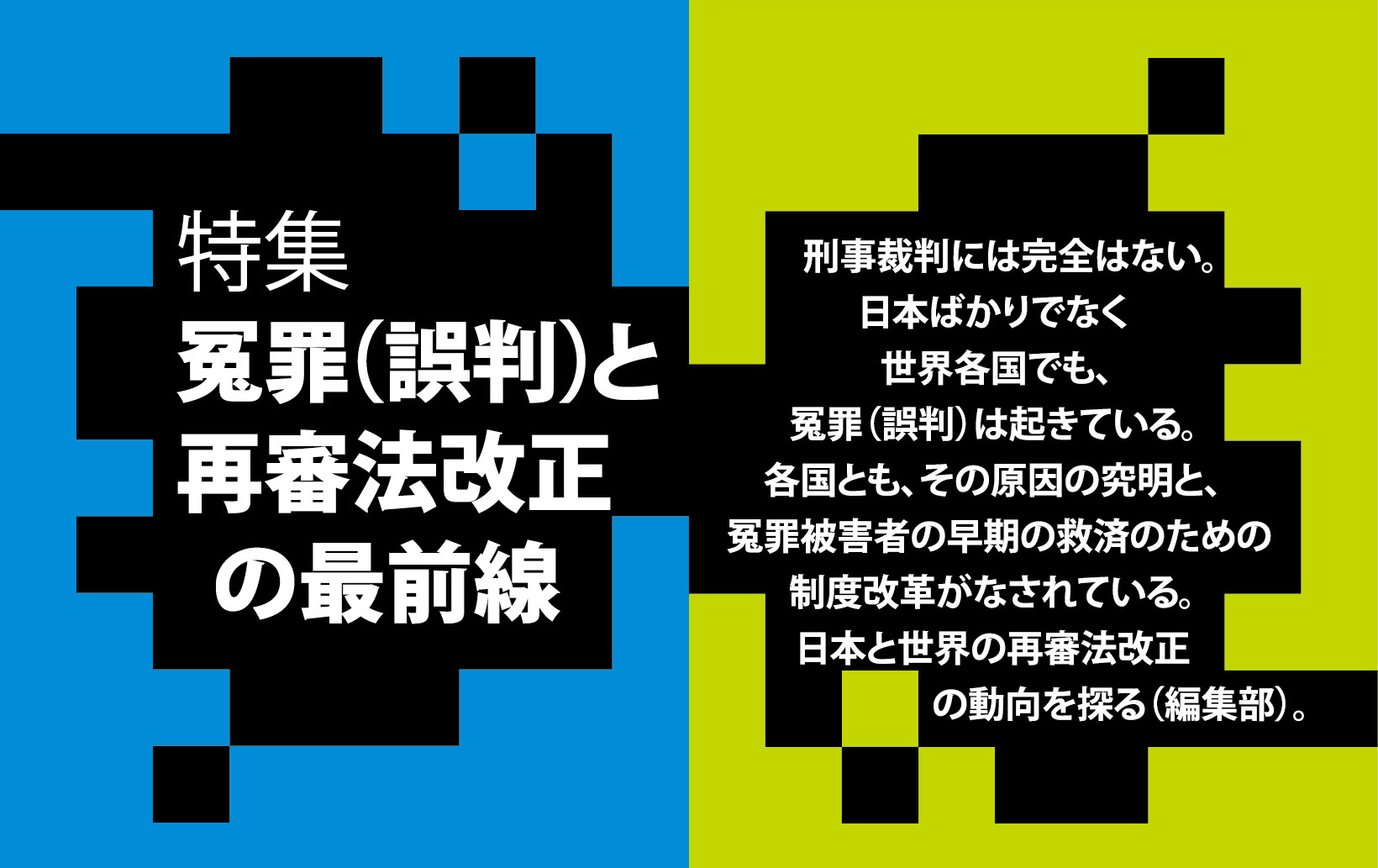4 各論点に関する各委員の発言(その1)
前回では、論点整理と議論の進め方について報告した。今回より、各論点についての各委員の発言の概要を整理し、2回に分けて報告する。第1の⑴「再審請求審における閲覧・謄写に関する規律」からはじめる。
【「再審請求審における閲覧・謄写に関する規律を設けるか」について】
① 制度の枠組みについて
まず、規律の要否と、制度の枠組み(「直接開示型」か「裁判所提出型」か)について、研究者(宇藤崇委員、川出敏裕委員、成瀬剛幹事)から、制度の必要性は肯定した上で、以下のとおり「裁判所提出型」によるべきとの意見が出された。
宇藤委員:再審請求審の審理が適切に行われるために、規律は是非とも必要。
規定がない中で手探りで運用していることが混乱や遅延の原因となっており、規定は必要。通常審における証拠開示制度が手掛かりとなるが、確定判決があることを前提として、再審に理由ありと認めて初めて再審公判となる再審請求審と、必ず審理が行われる通常審とでは制度の立て付けが異なる。通常審の制度のうち、争点関連証拠開示が参考になる。それ以上の充実を否定するものではないが、現行制度との整合性を踏まえた比較対照はしやすい。
川出委員:鴨志田委員から提出があった事件の概要と問題点をみると、不提出記録の中に、裁判官が再審理由の有無の判断に資する証拠があることは確かである。一方、明文がない中での判断は裁判官にとっても悩ましい問題である。必要な証拠が出るという側面と裁判官の判断に資するという両面から必要な法整備を行うべき。
再審請求審において、検察官は当事者ではない。再審請求審は、請求人・弁護人と裁判所との二面構造であり、再審請求に理由があるか否かを裁判所が主体となって明らかにする手続である。裁判所が審理に必要があると認めたものについて、検察官に対し、その提出を命じる制度とすることが、構造的にも実質的にも妥当。
成瀬幹事:再審請求の審理は、職権により裁判所が主体的に行うこととなる。裁判所が審理に必要と考えた証拠について検察官が裁判所に提出するのが再審請求審の構造に適合する。弁護人は刑訴法40条1項に基づき、閲覧・謄写することができるので、弁護人の活動に支障は生じない。
主張と関連付けられないまま、証拠を弁護人に開示させて主張立証させるのが合理的とは思われない。このような制度は、当事者主義的発想の裏返しであり、職権主義的構造とは整合しない。
これに対して、日弁連の委員・幹事は次のように反論した。
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年08月02日公開)