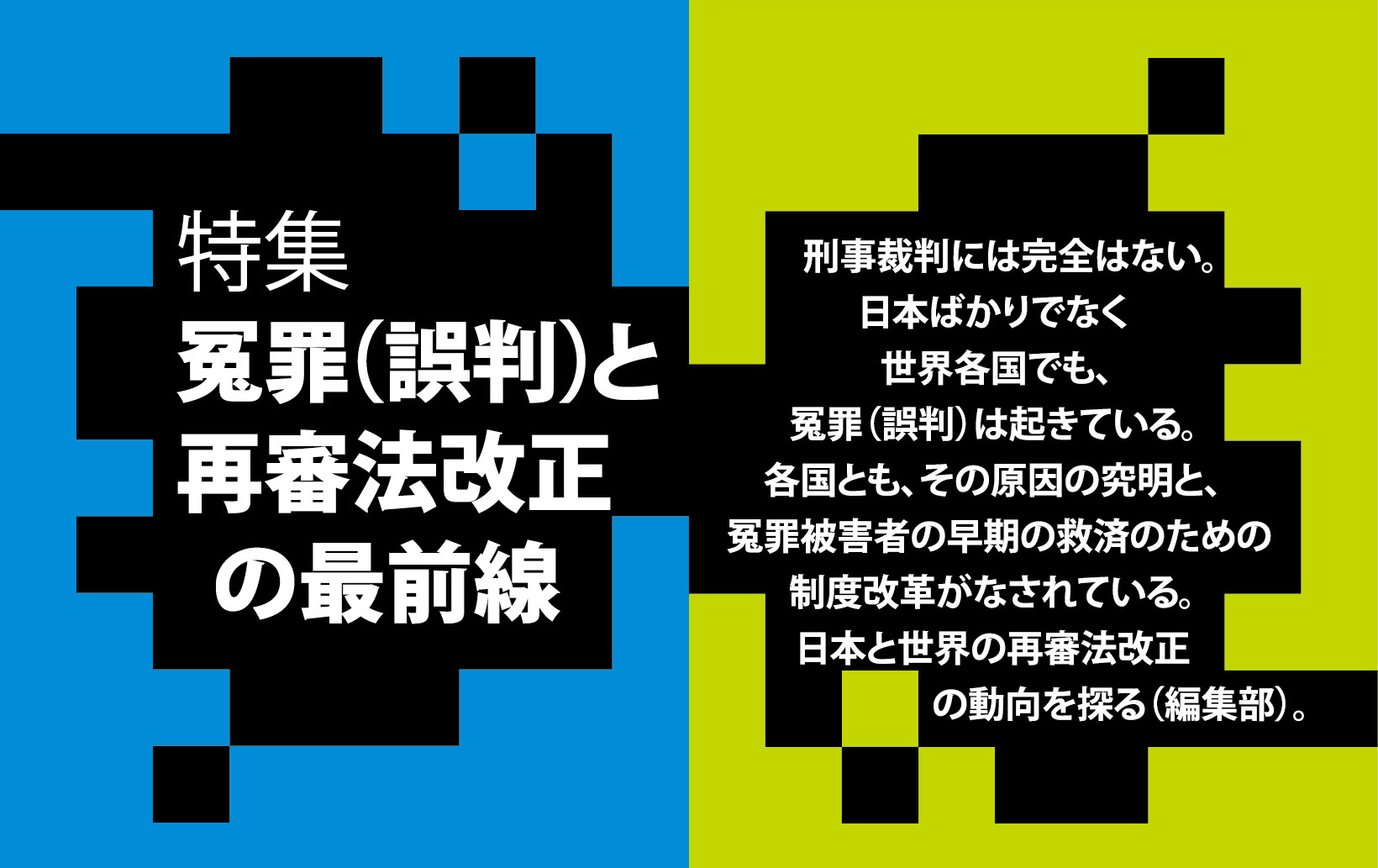前回に引き続き、第4回会議で検討された各論点のうち、⑵「再審請求審における検察官による証拠の一覧表の提出」、⑶「再審請求の準備段階における閲覧・謄写」、⑷「再審請求審において閲覧・謄写した証拠の目的外資料の禁止」について報告する。
【「再審請求審における検察官による証拠の一覧表の提出に関する規律を設けるか」について】
この論点については、まず筆者が口火を切った。
鴨志田:これまでの再審請求において、裁判所の訴訟指揮によって証拠の一覧表が開示された実例として、日野町事件第1次再審請求審があるが、極めて稀なケースである。検察官は証拠の標目の開示については証拠そのものの開示以上に消極的であり、裁判所が「証拠の存否を調査して、存在する証拠の標目を開示せよ」と勧告した事例(松橋事件、大崎事件第2次即時抗告審)、「警察が検察に記録を送致した際の送致目録を開示せよ」と勧告した事例(飯塚事件第2次請求審)でも標目の開示を拒否している。
しかし、再審請求人にとって、捜査機関が保有する公判不提出記録・証拠の実情を把握することは不可能であり、証拠の標目が示されなければ、手掛かりもないまま当てずっぽうに個別の証拠の存否を問い、これに検察官が回答することを繰り返すというやりとりが延々と続き、膨大な時間を要することになる。現に、証拠の標目開示請求が認められなかった布川事件では、2度にわたる再審請求で弁護団が繰り返し個別証拠の開示請求を行い、その結……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年08月03日公開)