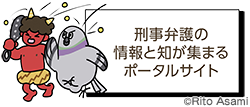思いがかたちに——公判~評議
「なんで火をつけたんですか? どうしてそうなったの?」って聞いたんだわ。そうしたら、「自分のほうを見て欲しかった」って。お父さん亡くなって、お母さんと2人になって、たぶんお母さんも生活で精一杯で、きっと話を聞く余裕もなかったんじゃないの? それに、お父さん亡くなってから、叔父さんや叔母さんにすごく言われてたというかいじめられて、責められていたって。母子家庭になって家に戻ってきたら、叔父叔母からやっかまれて……。本当、心痛かったよ。
お母さんに見て欲しくて、もっとお母さんと話し合いとか、ふれあいみたいのが欲しかったみたいな感じに私は受け止めたの。そこまで、火をつけて自分の気持ちを伝えるほどにまでなっちゃってたのは、とても残念だなって思ったもん。それよりも前に、黄色信号があったんじゃないの? 気づいて欲しかったってあったんじゃないかな。
やっぱし、考えが変わったよね。自分の子どもたちも同じぐらいの歳の頃に、自分も忙しい忙しいってしてたけど、そういうことじゃないんだなっていうふうに教えられた部分もあったね。
素朴な質問から、衝撃の真相が見えてきた。被告人が置かれた環境は、本人では選ぶことのできない現実だ。忙殺される母に届かない声なき声は、火の手をもって伝えるより他なかった。それに、叔父叔母からの理不尽な冷遇の根元には母子が出戻ってきた家屋、つまり相続対象となり得る不動産があった。「家がなくなれば、嫌がらせもなくなると考えたのかもしれない。子ども心にね」と小野さんは推察する。
そして、肝心の母親だが流れからすると証言台に立ちそうなものだが、「誰か女の人がいた記憶がある」がはっきりとは覚えていないそうだ。多少残念だが、おそらく母親で間違いないだろう。2日目の夕方には検察官から、「事件前に、放火しては自分で消すという実験を3回も行っていて再犯可能性が高い」として懲役5年の論告求刑があった。一方の弁護人からは、「執行猶予付判決で、もう一度社会内でチャンスを」という最終弁論があり、早々に結審した。翌日15時30分の判決公判に向けて、舞台は評議室へと移る。
弁護人のね、「彼はこんなことしてしまったけど、まだ若いし、幸いにも人が死んでないし、お母さんも面倒見るって言っているし、もう一度社会内でやり直すチャンスをください」っていう感じのお話でね。何人かが、「やっぱしまだ若いし、反省する気持ちというか、お母さんに対して気づいて欲しかったっていうウブな気持ちじゃないですか。だから、やり直しできるように執行猶予でどうなのかな?」という話はしてた。
私も、あーそういうやり方もあるんだって、それはいいねっていう気持ちになったもん。とにかくやり直しができる。そういう良い環境であればいいなって。執行猶予の説明があったかどうかはわからないけど、とにかくその後の彼を見ていきたい、生活態度がどう変わっていくのか、ちゃんと社会人として自分の人生をどうしているのかを知りたいって言ったら、それは保護観察だわって言われたの。
制度として理解してなかったけど、「月に1回、保護司と面接して真面目にやっていますという報告をする」というので、それはいいねって。私が思ったのは、お母さんに気づいて欲しかった。お母さん忙しいけども、(被告人を)お母さんの手元にいさせたかった。お母さんに寄り添ってもらえる環境を作りたいっていうのがあったよね。親の温もりがそこさ繋がるものだと思うんだ。
結論から言うと、評決は懲役3年、保護観察付執行猶予5年となった。保護観察という制度を知らない小野さんが母としての思い、素人としての発想で意見した結果が形になった判決と言える。当初、「素人が裁判員なんてできるのか」と捉えていたのだが、その素人の感性だからこそ導き出せた結論なのだろう。
一方で、保護観察付の執行猶予5年は執行猶予の中でも一番重いと言える。その背景にはこんなやりとりが影響していたのかもしれない。
「とはいえ、今回はたまたま人が死んでなかっただけで、運が良かっただけの話。ともすれば、人が死んでいたかもしれないし、隣の小屋も全焼していたかもしれない。これを次は気をつけろよ、で済ますのはよくない」っていうふうな話があって、あらま、そういう考えもあるんだって。でも、そういうご意見があって確かだと思うし、人生はそんな甘っちょろいことばっかしじゃないし、それはもう貴重だと思いました。
意見の食い違いとは別次元で、小野さんにとって貴重な視点だったようだ。いずれにしても、執行猶予5年を「言葉では簡単だけどやっぱ長いよね。ちゃんと罰になっている」と捉えている。ちなみに、裁判長や裁判官の発言や量刑検索システムも「あったかもしれないけど、私の記憶にはございません」だそうだ……。
新しい空気が吸えた——判決~裁判後
最終日、判決公判の直前まで深い議論を重ねて行き着いた判決を被告人に言渡す。
その場面は思い出せない……。けども、「処する」という言葉ってすごい重いなって思ったのは確かだね。(被告人は)前向いてたか、下向いてたか記憶にない。不満そうではなかったです。懲役3年(保護観察付執行猶予5年)に処する……。
記憶の断片に残る「処する」という言葉。小野さんには強烈な印象となったのだろう。無事に3日間の裁判員の務めを終えた彼女は、裁判所をあとにして職場への報告をした。
「無事に終わりました。3日間ありがとうございました」って言ったら、「お疲れさん」ってそんな感じで、事件のことをどうだったこうだったっていうのは聞かれなかったし、話さなかったな。
主人もね、(通知が来た)最初の頃だけで、その後はどうだこうだっていうのは聞かれた記憶ないな。聞かれても何も言わないけど(笑)。子どもたちには、そういえば言ってないな。今も知らないね……。みんな家から出て10年以上で、盆とか正月に遊びに来るくらいだね。そういう時に話題にしてもいいかもね。
もしかすると、家族の中にも裁判員経験者がいて、家族の話題に広がりが出るかもしれない。小野さんに聴くのは野暮な質問かもしれないが、裁判員を務めるにあたって多少でも負担はあったのだろうか。
全然、全然(笑)。事件の重さとかもあるし、人にもよるんでしょうけど、私はこういう世界があるんだなって、新しい空気が吸えた感じ。普段の仕事より楽だったし。
裁判官が、おやつ出してくれたり、「青森の雪には驚いたけど、食べ物は美味しい」とか、そういう話をしてくれたりしたのは有り難いし嬉しかったね。そんなに深い話をしたわけでないけど、固いお仕事っていうイメージがあったから、そういう人間同士としてのお話ができるっていいよね。
どこまでも前向きな方である。やはり、お茶やお菓子などを介在して場が和むのは、小野さんが歩む茶の道に通じているのかもしれない。インタビュー後に知らされたのだが、用意していただいた部屋には、津軽金山焼に活けられた二人静が楚々と佇んでいた。そんなさりげない気遣いこそが彼女を人格者たらしめる。
あらためて、今回の裁判員経験から小野さんは何を学び得たのだろうか。
やっぱし、社会勉強できたね。介護やお茶やお花の世界とは全然違う。新しい空気を吸えた。もっとこうガチガチにやるもんかなって思っていたけど、そんな堅苦しいことはなかったし、おやつでもなんでも、そういうところが柔らかくさせてくれてた。
今でもいろんな事件がありすぎて、とても残念なことばっかしだけど。でも、こういう事件がありましたというニュースを見ると、じゃあどんなふうな裁判になって、何年くらいの刑になるんだろうっていうふうな興味が出ましたね。それまでは全然興味なかったのに。
振り返ると、とにかくどうしてなんでっていう疑問ばっかしで、この子(被告人)と自分の子と(比べた時に)、あぁ私も一つ間違えればそういうこともあり得たのかなって。ただただそういう気持ちだったね。やっぱし、何があってもおかしくない。親としては常になんかかんか心配事はあるわけですよ。
繰り返される「新しい空気を吸えた」は、知らなかった世界を新しい刺激として吸収できる素直な心から生まれる言葉だと思う。そして、図らずも自身の子と被告人が重なるような事件に遭遇し、自分自身を見つめ直す機会にもなったようだ。

「身元引受人できませんか?」
ところで、小野さんとの交流が始まったきっかけは、冒頭の「死刑執行停止の要請書」ではない。それよりも前に弘前大学の平野潔教授を通じて、彼女からこんな相談を受けたのが始まりだった。
裁判員やったすぐ後に、職場の同僚が性犯罪(強制わいせつ致傷罪——現不同意わいせつ致傷罪)で22年刑務所に入らないといけなくなって、青森から出る(移送)前に、親にも兄弟にも「身元引受人」を断られたから、「小野さん、できませんか?」って手紙が来たの。それで、どうしたもんかって相談したの。
警察の人が職場に来て、車を1台1台チェックして、その人が来たところで逮捕。その前々日だったか、夜勤で施設にいたら、その人が手の指にケガをして来たんですよ。「小野さん、シャワーしていいが?」って。その後、「朝まで少し寝させて」って。そのまま朝の仕事してたんだわ。
個人的なことだが、裁判員を経験後に受刑者の社会復帰を支えることこそが、犯罪の少ない社会への近道と考えた私は、何人かの身元引受人を担っていた。弘前大学で講演した際にそのことに触れ、それが小野さんの耳に届いたらしい。しかし、詳しくは書かないが自身の経験からも、彼女にその任を背負わせるのは避けたほうがよいと考え、文通程度はよいが身元引受人は断ることを助言した。
結局、引き受けてない。どこにいるかもわからないから面会とかも行ってない。でもね、(逮捕前に)「俺は小野さんが思うようないい人間じゃないですよ」って言われたり、「お寺さんって行けば、すぐ住めるんだが?」って聞かれた時があったの。「お坊さんになりたいって、修行したいって言えば受け入れてくれるところもあるよ」って教えてあげた。
社会の中で真面目にやりたいけど、何かその煩悩みたいのを断とうというのがあったのかね。家庭環境もよくなかったみたいだったし。
その方の裁判員裁判を傍聴までしていたそうだが、「引き受けていない」と聴いて安心した。どんな人に対しても、等しく真面目に優しく接する小野さんだからこそ、身元引受人は不向きだと思う。賛否はあろうが私は彼女がショックを受ける姿を見たくない。
深く考えずに自然に
そんな小野さんと出会ってから10年以上もの間、ずっと念願だったLJCC(Lay Judge Community Club)での青森(東北)交流会を2023年に実現することができた。翌年には、彼女が「茶事」を催すために所有する古民家「蔵」の場所を提供していただき、LJCCで初となる会食様式での交流会を開催した。
「蔵」は、在宅介護でお世話させてもらっていた方から、縁あって購入させてもらったの。LJCCもご縁です。自分も裁判員に選ばれて、正直、何がなんだかわからなかったけど(笑)、自分に与えられたこととして、これをやりなさいよと言われたものと受け取ってるんですよ。自分の人生の勉強でもあるし、ご縁があっていろんな方との出会いもあるし。
小さい頃から、人のご縁は大事にしなさいよとか、人に喜ばれること、世のため人のためにって教えられてきたもんで、こんな私でも何か一つでもやれることがあるんじゃないかなって、そういう気持ちでいっぱいです。まわりからは、「なんでそこまでできるの?」って言われる。俗にいう「おひとよし」(笑)。
恩着せがましい気持ちなんかなくて、自然に喜ばれたらそれで良いっていう単純な考えです。なんも深い意味はないんです。深く考えているんじゃなくて、自然にそうなっているの。


実家も嫁ぎ先も、神仏への信仰があるとのことだが、それだけではない小野さん自身の人間力を強く感じる。最後に、もう一度裁判員の機会が巡ってきたら、と問うてみた。
あーやるやる(笑)。今度はちゃんと自分なりに準備して行きたいね。与えられたものなら、(どんな事件でも)来たものは引き受けて、冷静に判断できるかな。でも、あと2、3年で70(歳)だから断れるんだ(笑)。
きっと、小野さんならいくつになってもどんな状況でも、来いと言われたら行くし、選ばれたら断らない。深く考えずに、いつも自然体の彼女だからこそ「なんとかなる」と言い切れる。
(2025年6月5日インタビュー)
【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】
・第8回 それはそれ、これはこれ(濱清次さん)
・第9回 コロンボの思考(大木春男さん)
・第10回 同じ裁判、別な視点(山下美紀さん)
(2025年11月14日公開)