他の自治体は続々とプロジェクトを始めていた
行政手続きをオンライン化することで職員の負荷を軽くし、新しいことに取り組もうとしている自治体は少なくない。
「どれをとっても面倒な行政手続きをアクセスしやすくする、住民の利便に資するサービスを作りたいと、私はエンジニアとして思っていました」
中嶋さんはBot Expressを立ち上げる前、LINE株式会社に勤めていた。そこで着想したのがLINEを使った行政手続きのオンライン化だ。
はじめに手掛けたのは、福岡市とLINE社でパートナシップを組み、LINEを通じて粗大ごみの申請をできるようにするサービス。LINEで行政手続きをする全国初のサービスだったという。
「それまでも、市町村の公式LINEアカウントなどはあった。でもそれは自治体がマーケティングのために使うにとどまっていて、住民側のニーズに応えるものではなかった」中嶋さんは振り返る。
「私たちが福岡市の粗大ごみ申請のサービスをリリースしたところ、利用率、フィードバックともに、想像をはるかに超えた圧倒的な支持を得ました」
LINEを通じた受付が始まった後、電話での受付数が減り、LINEからの受付数はウェブサイトでの受付数を大きく上回るようになったという。
「はじめは市町村も、LINEという一企業が提供するアプリに依存するようで躊躇(ちゅうちょ)があったようです。しかし、ふたを開けてみると圧倒的な利用率があった。建前上の公平さより、住民の利用率を上げることの方が重要なのではないかと、自治体も取り組みを通して分かってきたようでした」
「そこで私たちは次に、行政手続きの中でも特に利用量が多く、それゆえになじみが深くて『面倒』な、住民票申請に取り組もうと考えました」

事実上「住民票申請機能」が利用不能に
中嶋さんの『GovTech』チームは、次は千葉県の市川市と組んで、住民票の申請手続のオンライン化を始めた。市川市のサービスは着想から半年でリリース。当時の平井卓也IT政策担当大臣にも話し、応援を受けた。
もともと区としてLINEを使っていて、「新しいことをやりたい、職員の負荷も下げたい」という意識が強かった渋谷区でも、すぐにサービスの提供が決まった。他の自治体からも話が来ていた。その矢先、渋谷区のサービス提供開始から2日後の、総務省の通知だった。
Bot Expressの提供する住民票申請は、「役所をオンライン化するサービス」の中の一機能。「そのほかにもいろいろとサービスを提供していますので、ビジネス自体が停滞しているというわけではないです」と中嶋さんは言う。
「でも、総務省の技術助言が出た後に、住民票申請機能を導入した自治体は、一件もありません。60ほどの自治体と組んでサービス提供していますが、一件もない。これは明らかにいびつ。明らかに総務省の通知の影響でした」
通知を出した総務省の自治行政局・住民制度課には、中嶋さんも説明に行き、市川市の職員も、渋谷区の職員もコミュニーケーションをとっていたという。
「ただ、もし総務省の見解が自治体の見解と違って『このサービスは適法でない』というものだったとしても、最終的に適法かどうかの判断は裁判所が決めることだと、私はそのときから思っていました」
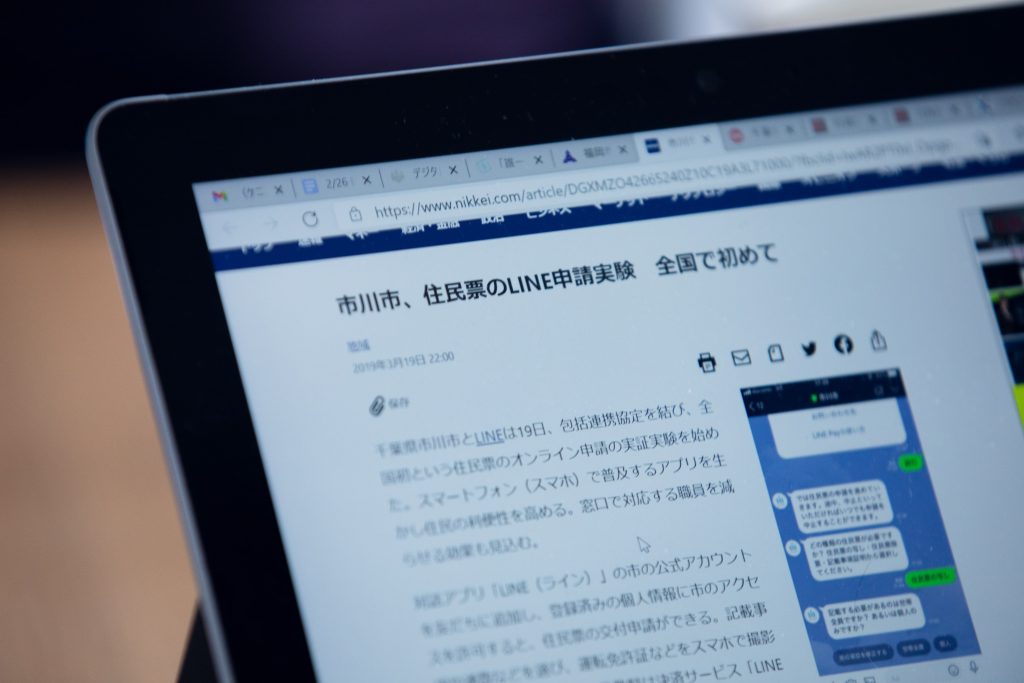
提訴に至るまで
もともと、サービスが適法か(規則4条2項但書に該当するか)は、裁判所が判断するべきと思っていたという中嶋さん。「裁判を起こしたのは、一言でいえば、やっぱりやるべきだと思ったから、に尽きます」
「ロビイングもしました。与党の議員さんにも会いましたし、各党の勉強会などにも行った。世の中にも訴えたし、自治体にもコミュニケーションをとった。ロビイングに関してはこれ以上やっても効果は出ないだろうという感がありました」
「それでも、うちがやらなかったら、この問題は放置されてしまう。やるべきことはすべてやらないといけない、残る手段が裁判であればすべてやり切るべきだ、と、夏ごろに提訴を決めました」

『紙縒り(こより)』で綴(と)じなければならない仕組み
「これだけ技術イノベーションが起こっている時代にもかかわらず、自治体のITシステムを使った行政サービスって、あまり変わっていない。なぜこの化石みたいなシステムが続いているのか」中嶋さんは問いを立てる。
一つの理由は、「この領域が閉鎖的な業界で、規制も多いが参入障壁も高い」ということがある。しかし参入障壁は数の問題だけではない。
「官公庁とのプロジェクトは、一つの案件に対する負荷的な労働が非常に多い。面倒なプロセスを経ないと自治体との契約自体ができないとなると、スピードを求めるIT企業はなかなか一緒にやっていけません」
「たとえば先日、入札のための資格申請の手続きがありました。書類を法務局に取りに行ったり、大量にダウンロードしたりするのですが、極めつけが、書類を『紙縒り(こより)』で綴(と)じてくださいというものでした」
紙縒りとは、細かく裂いた和紙をより合わせて紐にしたものである。閣議で使われる書類の「紙縒り綴じ」廃止を河野太郎行政改革大臣が提唱したのが、この訴訟の提起後、つい数か月前の2020年10月だった。
「行政機関ではルールを前提に考えるため、いったんルールが作られると、そのルールの妥当性について能動的に検証がおこなわれることはほとんどないと感じます。だから紙縒りの話も、これってなんだかおかしくないか?って、気づかない。根本的に、何でこうなっているかを考える習慣がないように思います。それが、「常に改善していく」という姿勢にならず、仕組みが化石のようになっていく原因の一つだと思います」
「ルールに依存しすぎている。何のためのルールかを考える余地もない。ルールを作った後は、ルールであれば問題がないという発想になることが、あまりに多い」
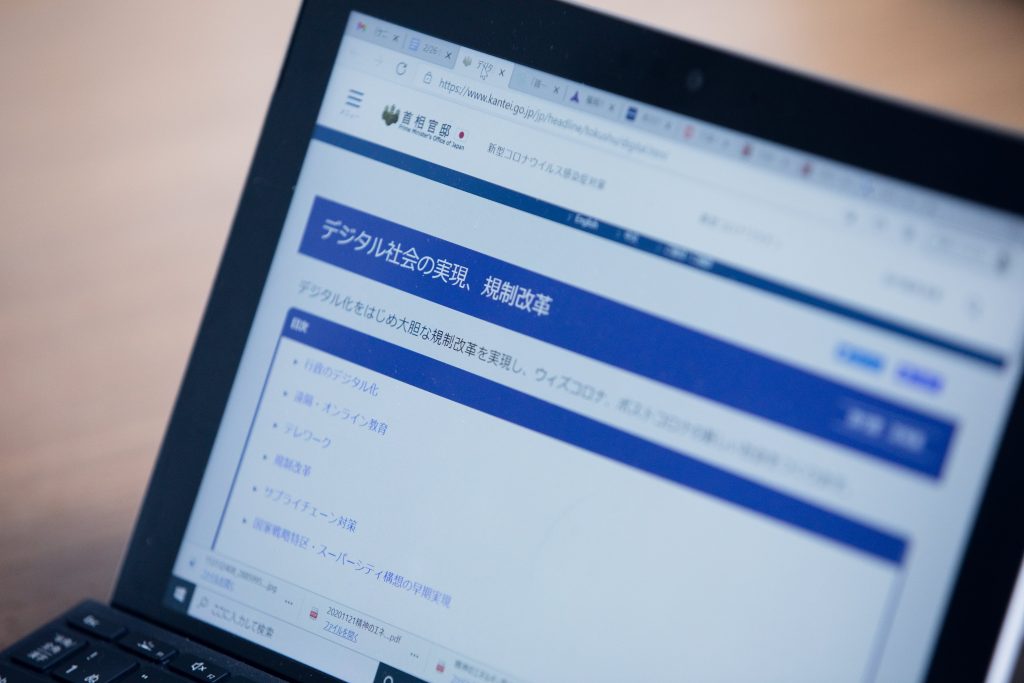
自治体とイノベーションの未来
「自治体側がそれを変えるのに必要なのは、ひとえにリーダーシップ、ビジョンを提示する首長の存在だと思っています。そして私たち民間側でできることもある」
「私たちがやるべきことは、成功事例を作ることです。自治体の中に、共鳴する人、新しいことをやりたいという一部の人を見つけて、プロジェクトを一緒に立ち上げ、実現させる。3カ月から6カ月の短いスパンの中で成功事例をまず作る。一度成功すると、自ずと展開されていく可能性が高い。」
「誰かがやっていると途端にハードルが下がって、次が続く。そして、粘り強く取り組みを継続していればそれが新しいデファクトスタンダードになっていく。」
「自治体もサービスをいろいろとやってみて、実際に広く使われたプロジェクトや、満足度が高かったプロジェクトは何かを判断し、多く使われたものに予算を投入するようになればいい」と中嶋さん。
「今の国のスタンスからは、フィードバックを得るプロセスが欠落している。やった事業を正当化するというスタンスばかり見える。何を評価の指標にしているか、事業をやってどういう効果があったかを可視化して、客観的に評価するべきです。事業を適切に評価できないと、意味のなかった事業を意味がなかったと言って終わらせることができないままになります」
今回の裁判が始まってから、「まわりの自治体はみんなこの裁判のことを知っている」と中嶋さんは言う。自治体ネットワークは全国にある。多くの総務課や経営企画課がこの裁判の行方を見守っているのだという。
取材を終えて
「技術が進化している」といわれる時代に、日本の行政手続きのオンライン申請の割合が低いというのがずっと不思議だった。「紙縒り」という言葉を10年ぶり以上に聞いてすこし理解した。紙縒りが標準設定になっている世界が10年以上続いている。
そこを変えていくためには内部からも外部からも自律的に考えた働きかけが必要になるのだ、そしてそれは「訴訟レベル」の働きかけになるのだと。

(2022年04月15日) CALL4より転載


