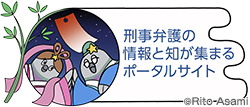弁護人に必要な質問する力
弁護人の強さって、どういうところだと思いますか。例えば「刑事弁護人だと、こういう力があると強いよね」とか。
検察官とあまり変わらない気がします。もちろん、弁護人は調書は取りませんけど。僕らの仕事はやっぱり質問する力ですね。
人の頭の中にはいろいろな情報が入っていますが、それを取り出すのは質問です。どんなにいい証人でも、証言を引き出せるかどうかは聞く側の力にかかっています。
自分ができているわけではありませんが、その人に応じて、その人に合った日本語を駆使できないとダメです。例えば、目の前に弁護士がいるなら「共謀共同正犯は……」なんて言ってもいいですが、ヤクザがいたら「共謀」なんて言ってもわかりません。子どもだったら子どもにふさわしい言葉遣いがあるでしょうし、異性でも、お年寄りでもそうです。
これは、なにも弁護士に限った話ではありません。ただ、相手に応じて言葉遣いを変える力は、検察官よりも弁護士のほうが早く身につくかもしれません。いろいろな人が舞い込んできますから。特に民事はそうです。
「おっ!」という驚きは、民事のほうがありますね。親族同士の争いなんて、検察官をやっていると想像がつきません。
そうか! 確かに、検察官の仕事はそこには関わりませんよね。
検察官をやっていても、離婚事件の「リ」の字もありません。「離婚しそうになって人を刺した」だったら、「刺した後」からはわかりますが、「刺す前」の法的なことはよくわかりませんでした。もっとも、検察官時代の僕が不勉強だったからだと思いますが。
へぇー。
だから、おそらく弁護士のほうが質問に神経を遣うのではないでしょうか。お金を頂戴している人に、ときには失礼な質問をしなければならないのは、神経遣いますよね。
確かに。質問するときに、相手によって言葉を使いわける他に、何かコツはありますか。
誘導尋問をしない力ですね。5W1Hでいつも聞けるかどうか。事前に準備をすればするほど、事件の知識が入ってくるから誘導尋問っぽくなります。
そうか。
例えば、こちらが「あのとき、こういうことがありましたよね?」などと変な道筋を作ったばかりに、気が弱い人は「うん、まあ、そうなんですけど」と不本意な答えをすることになりかねません。「あのとき、何があったんですか?」と質問すれば、「こういうことがありましてね」ということになります。これも弁護士に限った話ではありませんが。
全部に通じそうな気がします。
信念と客観視は別物
弁護士に必要な力って何でしょうか。
気の強さですかね。僕は気が弱いから弁護士に向いていないのではないかと、しばしば思います。世界中で自分一人しかこの説を言っていないときでも、物おじしない気力がないと務まらないですね。僕は、その辺は全然ダメです。
目の前の被疑者・被告人を弁護しなければならないときは、「世界中の全員があなたを責めても、俺だけは守る」と本気で思えていないと負けます。「そうじゃない。この人にはこんな事情があったんだ」「そうじゃない。この人はやっていない」と、ちゃんと言えるかどうかで変わってくるので。
精神論みたいに言うのもなんですが、そういう気力みたいなものがあると、ここ一番のときに、その弁護士から出てくる言葉やたたずまいが違います。信じてやっている人間と、金をもらったからやっているだけの人間では、絶対に違います。
それをどうやって磨くのでしょうか。
ただ、信じ過ぎているとまた危ういので、バランスが必要です。信念と客観視は別物ですから。証拠をきちんと見たうえで信念を持てるかどうかです。信念だけでいいなら、変な話、法律家の資格は要りません。その意味で、検察官も本当は信念よりバランスが必要です。
『ナリ検』に書かれていたように、「弁護士から検察官」みたいケースはもっと増えてほしいですか。
極端な話、法曹一元が制度化されるべきではないかと、僕は思います。もともと日本では、まず議論にならないでしょうね。『ナリ検』は、結局、検察の現状に対する絶望から生まれた話なのです。検察は、ずっと昔からいろいろな問題を指摘されています。特に刑事弁護をやっている人から。でも、変わりません。
その法曹一元というのは、どういうことですか。
簡単にいうと、すべての法曹はまず弁護士になって、そこから検察官や裁判官を登用するということです。
弁護士は官僚組織にいるわけではなく、民間人として一般の人と接する機会が多いので、官僚が陥りがちな、一般常識から離れて独善的になることが防げるという考え方です。アメリカではそうしているようです。
検察官と弁護士の両方をやってわかったことは、先ほども言いましたけれども、検察官は国から漫然と給料をもらっているため、「商売」をしている弁護士が持つ現実感が乏しくなることでしょうかね。検察官は、仕事をしていても、目の前の一件一件が自分の生きる糧なんだという意識は持ちませんから、その意味で浮き世離れしてしまう気がしますね。
法曹一元については、弁護士会がその実現に頑張ってきましたが、官僚的風土が強いのか実現していません。僕の印象では、日本人は元来「官尊民卑」つまり「お上」を信頼する反面、民間人をさげすむ意識が根強いため、弁護士は裁判官・検察官より格下に見られていると思いますね。
法曹一元になると、裁判官ももっと市民の気持ちがわかるようになるかもしれません。でも、現実の検察官の意識は変わっていないということですね。
変わったようでいても、それは小手先であって、根本的な検察の物の考え方自体は何も変わっていません。なぜかといえば、「社風」が変わらないからです。司法修習が終わるとすぐに検察官になり、そのままずっと検察にいれば、検察の社風に染まりますよね。まして、そうしないと上に行けないわけですから。
検察の社風にフィットしない人間は「こんなこと、やっていられない」と言って辞めるわけです。だから、検察の持っている組織の考え方に疑問を抱かない人だけが残っていく。となれば、検察に残っている人が検察を変えようなどと思うはずがない。
もし検察の考え方に不満があっても、辞めたくなければ、己を押し殺して、なんとなく面従腹背で生き残る。どうかすると思考を停止して、ロボットみたいに機械的に仕事をしてしまう。僕はこのタイプのダメな検察官でした。これらのタイプからも、組織を変えようというエネルギーは出てきません。だから検察は変わらないのです。
「検察には検察官しかいないから変わらない。だから外から人材を入れよう。それもヒラの検察官ではなく、初めから決裁官に登用しよう」というのが、『ナリ検』で訴えようとした、僕なりの検察改革案です。
(つづく)
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2021年05月10日公開)