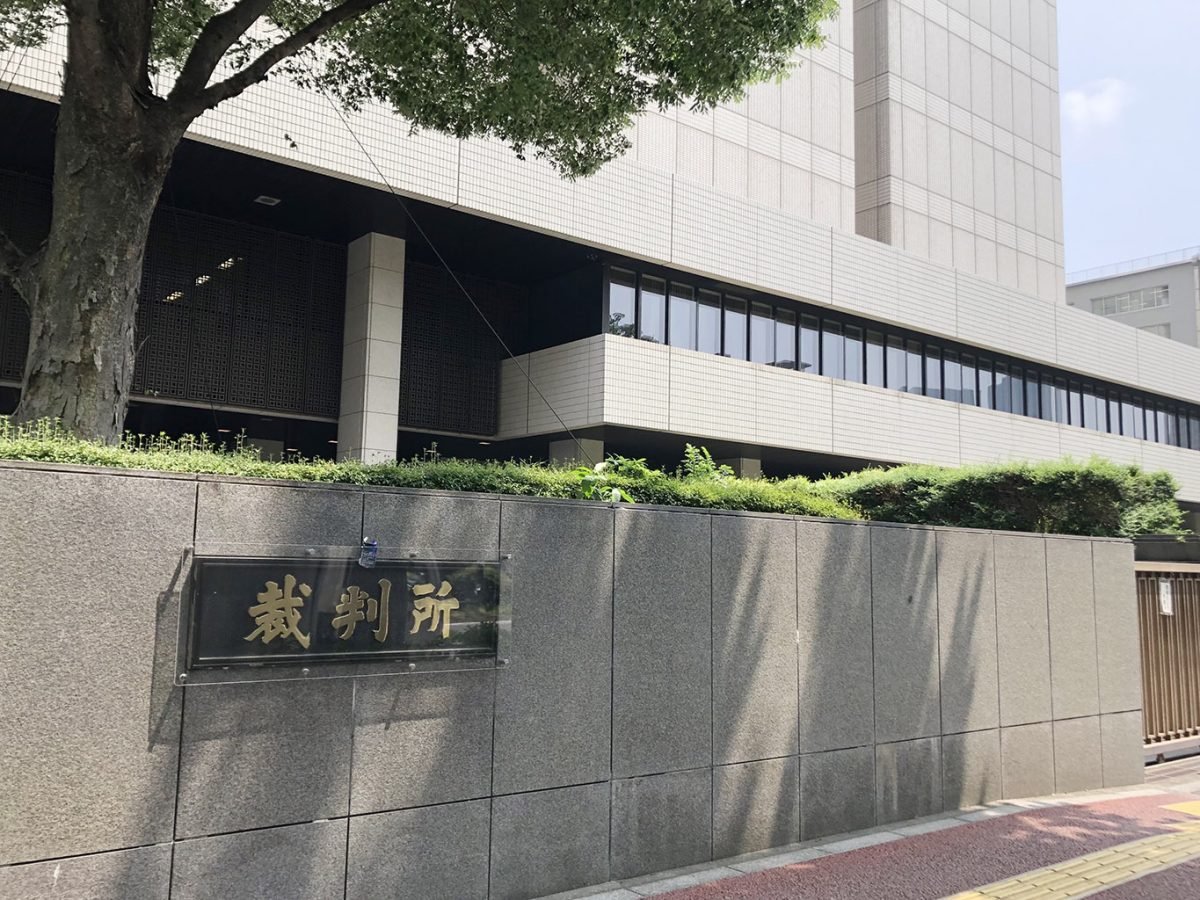
2025年7月9日、「人質司法に終止符を!訴訟」の第1回口頭弁論期日(裁判長:阿部雅彦)が、東京地方裁判所第626号法廷にて開かれた(提訴時の記者会見の様子はこちら)。本件は、「人質司法」すなわち、人としての尊厳や、これまでに築いてきた生活や生きがい、信用、財産など多くのものを奪う、自白を引き出すためとも思われる身体拘束に、終止符を打つことを目的とした国家賠償請求訴訟である。
有罪判決が確定する前に身体拘束をされた4人の原告が、自らの「人質司法」の理不尽さを訴え、身体拘束の根拠とされる条文、およびそれに基づく刑事手続の運用の違憲性を主張する。
失った時間、傷ついた心、奪われた信頼は戻らない
公判が始まる前、すでに626号法廷の前には傍聴希望者の列ができていた。法廷に入ると傍聴席はすぐに満員となった。追加の傍聴席がつくられたものの、座ることのできなかった傍聴希望者は、退廷となってしまった。
次回期日の日程調整など、事務的な手続を終えると、原告側の訴状要旨陳述へと移った。弁護団長の高野隆弁護士は、証言台の前へ進み、以下のように述べた。
我が国の憲法には、黙秘権、公開裁判を受ける権利、拷問の禁止、令状主義、そして、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば拘禁する理由を弁護人が出席する公開法廷で示さなければならないなど、「非常に詳細な刑事手続に関する人権規定」がある。
そこには、「曖昧な根拠で被疑者が何ヶ月間も拘禁されて、そしてその間に自白を求めて拷問が行われ」る戦前の刑事手続に対する反省があり、立法者の間では、「未決拘禁によって、被告人の公平な裁判所による公正な審理を受ける権利が侵害されてはならない。無罪推定が侵害されてはならない」という共通認識があった。
しかし、現在、上記の意図は実現されているだろうか。逆に、嫌疑を「否認している被告人は勾留され、いつまでも保釈が認められ」ない。いわば「自白を強要する」運用となっているのではないか。裁判官は、このような現状を知り、理解したうえで、立法者の意図どおりの刑事手続に改善する道を開いてほしい。
次に、原告の意見陳述が始まった。まず、出廷が叶わなかった天野さんと柴田さんの意見を、それぞれ鵜飼裕未弁護士と吉田京子弁護士が代読した。
天野さんは、「無罪を主張しているが、時計もない、弁護人以外とは話せない環境にいる。一般的に捜査機関への信頼感は高いが、このような境遇は珍しくない。自分の事件が『人質司法』のシステムを変えるきっかけになればいい」と述べた。
柴田さんは、「受刑中の今とは比べられないくらいに苦しい」。「話し方を忘れたようにな」る環境だった。「未決勾留には終わりが見えず、絶望しか感じられな」い、「精神的におかしくなってしまう」。裁判官の「型にはめるよう」な処理によって「ずっと人を箱の中に閉じ込めておける。この制度は間違っています」と述べた。
続いて盛本さんが、「身体拘束されているときには、特に捜査機関からは全く人間扱いされ」なかった。みな他人事だと思っており、自分もそうだったが、「人質司法」で「どれだけ心身に負担を強いられ、生活を壊されてしまうのか。この現実を多くの人に知ってもらい」たい、と主張した。
最後に浅沼智也さんが、「裁判が始まる前から罪人のように扱われ」、「『この苦しみから逃れるために、やっていないことを認めてしまおうか』と自問自答するほど追い詰められた」。これは「現代の拷問」であり、「失った時間、傷ついた心、奪われた信頼は、決して元には戻りません」と訴えた。
「人質司法」の実態を知ってほしい

公判後の報告会で、浅沼さんは、「助けてほしい、という声もなかなか届かず、拘禁されているときは心が折れる生活だった」と自身の経験を振り返った。そして、保釈許可の運用について、以下のとおり疑問を呈した。「同じ内容で保釈申請を複数回行ったが、裁判官が変わったタイミングで許可された。保釈を許可しなかった理由が何なのかわからない」。
これに対して高野弁護士は、「刑事手続の主人公である当事者個々人を見ずに、抽象的・類型的な理由で保釈をしない判断がなされている」と指摘した。さらに踏み込んで、「人質司法」は被疑者・被告人だけでなく、弁護人のアイデンティティ(存在意義)も崩壊させるという。弁護人が無罪主張に努めるほど被疑者・被告人の身体拘束が長引くからだ。
弁護団からは、「人質司法」をめぐる今後について、多くの人に実態を知ってもらうことが必要だ、という共通の見解が示された。弁護団の一人である宮村啓太弁護士は、「『人質司法』の現状は否定し難いのだから、今後は現状調査を実施したい」と展望を述べた。高野弁護士は、「『人質司法』の被害者が声を上げることも必要。角川さんが声を上げたのは、歴史的第一歩」と言う。
角川人質司法違憲訴訟の原告である、角川歴彦氏は、「『人質司法』の被害は自分だけが受けているものではない、すなわち未決拘禁の運用はマニュアル化されている、と気づくことが重要」と指摘した。そのうえで、「同じような経験をした人に呼びかけ、それぞれ違ったやり方で、『人質司法に終止符を打つ』という一つの目的に向かっていければと思う」と訴えた。
ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗氏は、「経験談を聴くほど、『人質司法』をめぐって闘い続けることは難しいと感じさせられる」と感想を述べた。しかし、「実際の運用を変えない限り、こういった国賠訴訟が続くことを、捜査機関・裁判所に認識してもらう必要がある」と本件の意義を語った。
原告の天野さんや盛本さんの言うように、国民の捜査機関への信頼度が高いとされる我が国において、「人質司法」を自分事と捉えることのハードルは高いのかもしれない。だが、冤罪は現に生じている。自分が「犯罪者」にならないとは言い切れないのだから、司法のあり方はすべての人に関係する問題だ。
本件の次回期日は、2025年9月24日(水)11:00〜、東京地裁第103号法廷にて開かれる予定だ。
「人質司法」の実態については、本サイトの特集「STOP人質司法!」、連載「取調べ拒否!RAIS弁護実践報告」(季刊刑事弁護120号〔2024年〕以降)、身体拘束をめぐる弁護活動については、戸舘圭之編集代表『勾留理由開示を活かす——勾留理由開示の理論と実務』(現代人文社、2025年)、 愛知県弁護士会刑事弁護委員会編『勾留準抗告に取り組む——99事例からみる傾向と対策』(現代人文社、2017年)愛知県刑事弁護塾編『保釈を勝ち取る——90事例の裁判理由からみる傾向と対策』(現代人文社、2021年)などがある。
(お)
(2025年07月16日公開)

