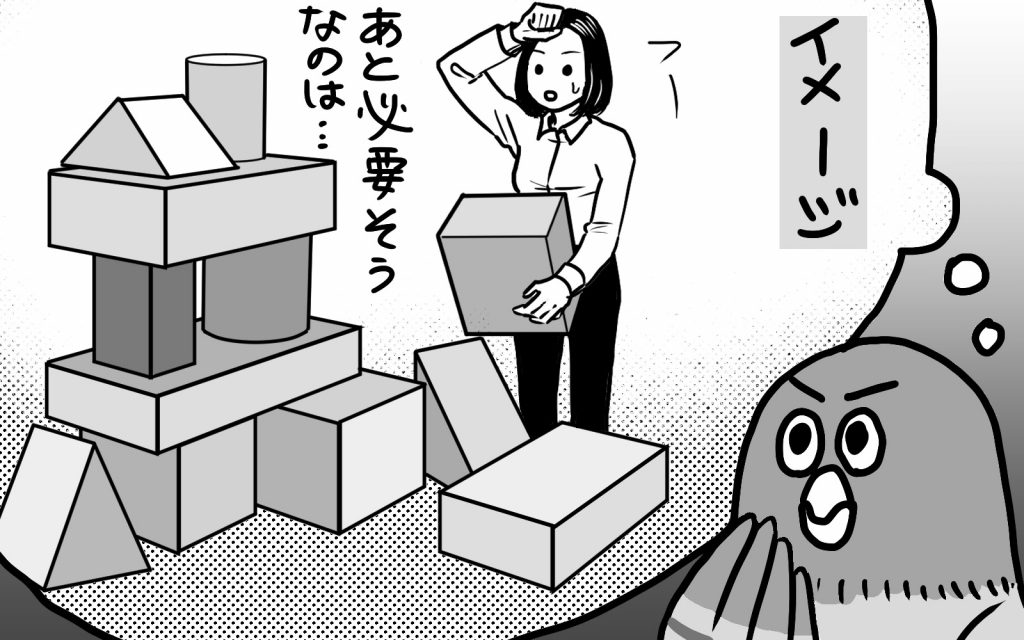
保護者とのコミュニケーションで気をつけていること
少年の親御さんとやりとりをしていく中で、何か気をつけていることはありますか。とてもデリケートな問題だと思うのですが、どうでしょうか。
私たちが担当するケースでは、少年本人から委任を受けるケースと、少年の保護者から委任を受けるケースとがあります。どちらかで多少変わりますが、最終的に「少年にとって何が望ましいか」という視点から考え、接するようにしています。
環境面があまり整備できていない親御さんもいるので、自分より年上の保護者の方にいろいろと意見を言い、必要に応じて改善を求めていかなければいけないこともあります。
例えば、発達障がいのあるお子さんだったら、発達障がいの特性を踏まえて対応してあげなきゃいけないわけですが、そのことに気づいていなかったり、受け入れられずに「何でできないの、何でできないの」って、ひたすら叱り続けているお母さんもいます。
歯車が合わないから、少年がひたすら反発して、家出が続くこともあります。親御さん自身も困り果てているケースもあれば、親御さん自身の能力に問題があって、対処できていないケースもあります。
良くない家庭環境であったとしても、少年にとってのかけがえのない親ですから、うまく歯車が合っていく方法は考えなきゃいけない。だけど、親御さんにも今までのさまざまな苦悩があると思いますので、単純に責めるっていう構造でもありませんし、できません。
実際には、主にお母さんですが、ケアの必要があるなと思うこともありますね。
実際は少年を担当してるけど、具体的にお母さんのケアにつなげたりすることもあるんですか。
14歳未満の少年の事件(触法事件)などで児童相談所が入っているケース等だと、お母さんのケアにも、ある程度結びつくことはあります。ですが、つなげるところまではいかないことが多いですね。
ただ、できるとすれば、お母さんの話すことを丁寧に聞くことでしょうか。1回電話をすると、1時間とかになったりするんですよね。お母さんも必死なんだなと思うことも多く、なかなかむずかしいです。
でも、そこまでやっていたら、付添人としての仕事の範囲外になっちゃいますもんね。
本当に、どこまでやるのかはむずかしいです。
最近、少年審判の家庭裁判所が、刑事裁判化してきていると言われることがあります。本来的には、その非行事実と要保護性との両輪で見るべきなのに、その審判の判断に占める非行事実の割合がだんだん増えてきているのです。
例えば、犯罪で誰かを殴ってしまったときに、刑事裁判的に言えば、被害弁償をすれば、それで量刑が軽くなったりします。それは犯情事実を中心として見たときに、弁償によって被害の総量が減少したと評価できるわけですから、当然の結論と言えば当然の結論です。
本来、少年の場合は、
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2021年11月12日公開)


