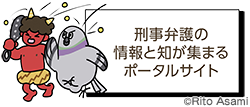初めまして。今回からコラムを連載させていただくことになりました、一般社団法人東京TSネットです。
東京TSネットは、罪に問われた障害のある人の支援をしている団体です。弁護士2人が共同代表ですが、福祉、心理、医療の専門職、障害福祉の現場に携わっている方、特別支援教育の関係者、障害のある人の家族等、多様な人に支えてもらい一緒に活動をしています。
障害のある人の刑事弁護では、障害のある人に思いを寄せて、障害や福祉制度についての基本的なことを理解したうえで効果的な弁護を提供することが必要です。しかし、東京TSネットの活動と同様に、障害のある人の刑事弁護も、弁護人だけでは成り立ちません。更に、障害のある人の刑事弁護が成し遂げようとしていることは、法廷の中や刑事手続の中だけで完結するものでもありません。
このコラムを読んだ弁護士の方には、「障害者の」刑事弁護の楽しさや難しさ、そしてそれが1人の依頼者の人生だけでなく、世界に与える影響を知っていただき、この分野を一緒に盛り上げてもらいたいなと思います。また、弁護士以外の方には、障害のある人の刑事弁護に取り組む弁護士が、どんなことを考え、どんなところで悩んでいるのか、刑事手続の中や外で障害のある人にどんなことが起きるのかを知ってもらい、社会の、罪に問われた障害のある人を見る目が少しでも変わればと思います。
障害のある人が犯罪を起こしやすい、というエビデンスや実証的な研究は存在しません。障害者は何をするか分からず危険だという考えは差別・偏見です。ところが、実際に刑事弁護に携わって……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2022年01月14日公開)