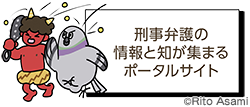人質司法に着目した理由(わけ)
── 報告書を読んでみると、傷害での逮捕といった新聞記事にも載らないようなレベルの事件もあります。こうした事件に着目して人質司法を取り上げるようになったきっかけは、そもそも何だったんですか。
土井 日本という国は、ヒューマン・ライツ・ウォッチのようなグローバルな人権の観点で見ると、人権状況が比較的いいと見られている国なんです。そういう国で、例えば弁護人が「取調べに立ち会えない」って言うだけでも、相当の驚きを持たれます。「本当に日本の話をしてるんですか?」って言われてしまうんですね。
私が、最初にヒューマン・ライツ・ウォッチの法務部にそのことを説明したら、「どこか別の国の話をしてるのかと思った」「いわゆる独裁国家の話かと思ったけど、日本の国の話なんだ」って驚いてました。最初は「『弁護人が立ち会う必要はない』って、言いましたか?」って聞き返されたくらいです。そうではなくて、「日本では、弁護人は取調べに立会えないんです」って言ったら、本当に驚いてました。G7のメンバー国にもなっている日本でそういうことが起き、長らく解決していないっていうのは、やはり驚きなんだと思います。
我々は、調査したうえでアドボカシー(政策提言、ロビイング)をする団体なので、「解決の目処が立っていない」という問題に切り込んでいくことには、意義があると思います。
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2023年10月27日公開)