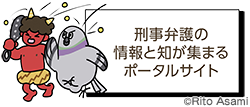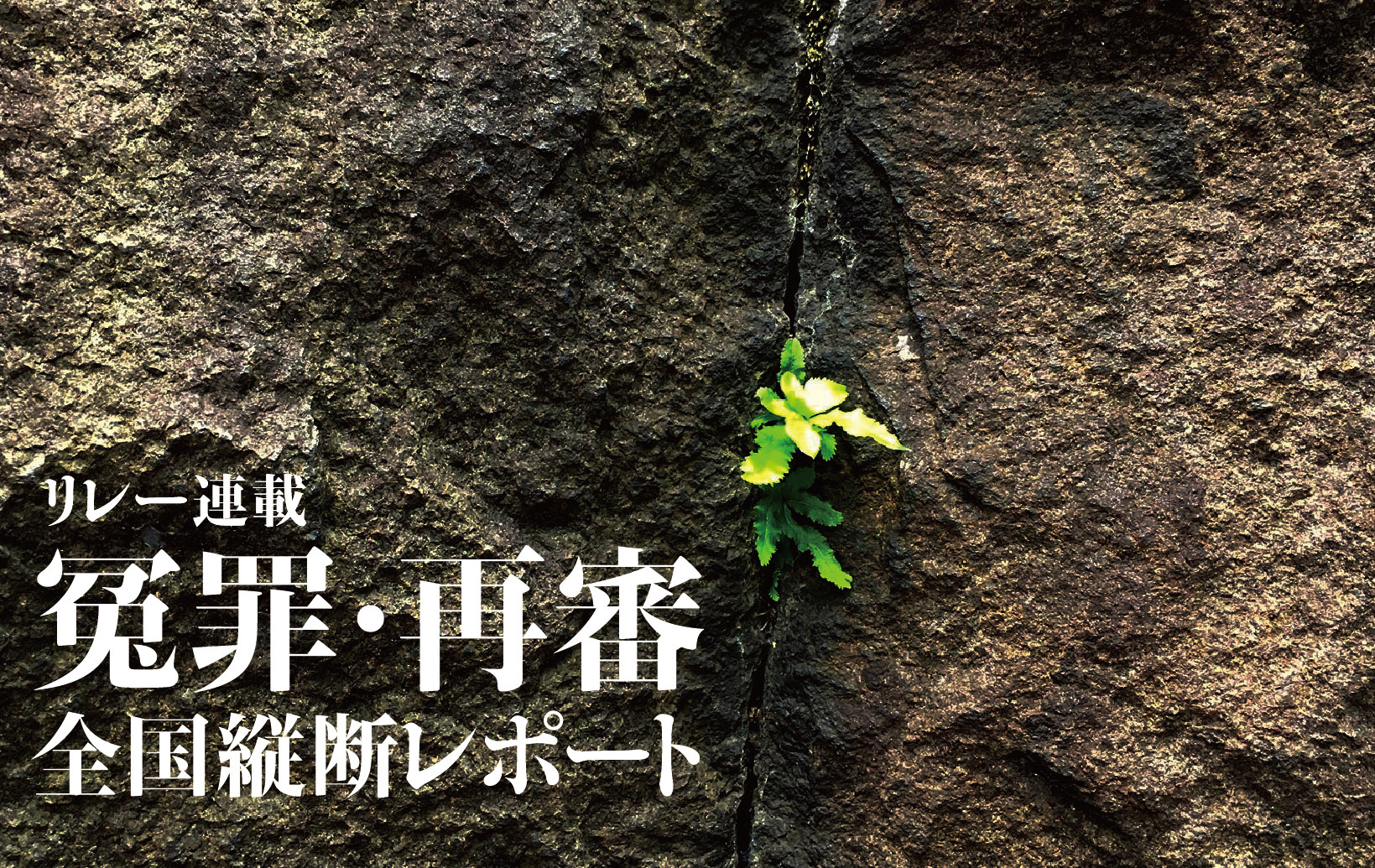⑵ 最高検察庁
再審無罪判決まで58年以上かかり、巖さんの法的地位が長期間にわたり不安定な状況になったことを「刑事司法の一翼を担う検察として真摯に受け止める」としながら「再審請求手続が長期間に及んだことや捜査公判上の問題点を検証し、今後、再審事件に検察が対応するに当たって講ずべき方策について検討した」とする。
再審公判でねつ造を全面的に否定していた検察が、それを認めるかどうかが最大の注目点だった。
報告書はまず、再審無罪判決は「事件の約3カ月後に袴田さんの衣類が寮から実家に送られる前に、捜査機関が5点の衣類を盗み出してねつ造したと認定している」とした上で、①当時、犯行着衣をパジャマとしていた捜査・立証の方針と齟齬する5点の衣類をわざわざ入手しておき、のちに犯行着衣としてねつ造することは現実的にあり得ない、②初公判で袴田さんが否認に転じる前から捜査機関が犯行着衣のねつ造を企図していたとするのは、客観的な時系列と明らかに矛盾しているとして、判決の認定は「合理的な根拠を欠いている」「客観的事実関係と矛盾する」と反論した。
しかし、無罪判決は、盗んだとも否認に転じる前からねつ造を企図していたとも認定していない。既に入手していた5点の衣類に血液を付着させるなどの加工をしたと推認したに過ぎない。誤解に基づく論難で失当である。
しかも、無罪判決が公判の経緯を仔細に分析して「捜査機関が5点の衣類のねつ造に及ぶことが現実的に想定し得る状況であった」と認定した部分を無視している。
5点の衣類の血痕の色合いを巡り、判決が「1年以上みそに漬かれば赤みは残らない」と判断したことに対しても「醸造の専門家らの見解を踏まえているとは認め難く、科学的な根拠を伴っているとは評価し難い」としたが、再審公判での5名の科学者の尋問は「醸造の専門家らの見解を踏まえて」十分に行われたのであり、審理内容を無視している。
5点の衣類の発見から12日後に押収されたズボンの共布(ともぎれ)についてもねつ造の認定に強く反発、検察官が共布押収の前日に5点の衣類を犯行着衣として証拠請求したのは不自然だと認定した点に対し、衣類の発見後に捜査機関が関係者の事情聴取などをしていたことを理由に「共布以外の裏づけ捜査結果を踏まえて5点の衣類が袴田氏のものだとの心証を得て証拠請求した」と主張。「検察官の対応に不自然・不合理な点は認められない」とし「明らかな事実誤認を前提とした認定がなされている」と判決を批判した。
しかし、無罪判決は、本来は慎重になるべきなのにたった2週間余りでガラリと立証方針を転換した点から(しかも5点の衣類に関する科学鑑定の結果も出ていない)ねつ造証拠を利用したとしているのであり、報告書は的外れである。しかも共布の発見は冒頭陳述変更の前日である。検察官がその報告を受けて疑問を感じなかった点も理解し難く、報告書の批判は皮相で検証に値しない。
そして報告書は再審請求審や再審公判での「検察の訴訟活動に問題はなかった」と結論づけている。
報告書は冒頭、無罪判決を批判するのは「あくまでも検察官の捜査公判上の問題点を検討するための前提」とし「無罪の結論を否定するものではなく、検察は袴田氏を犯人視していないことを改めて付言しておく」と釈明している。これは検事総長談話に対する世間の反発を意識したことは明らかであるが、釈明した理由を明示しておらず姑息な弁明としか言えない。
他方、報告書は警察の取調べに「多岐にわたる問題点が存在した」とし、検察は「警察官による取調べの影響を明確に遮断して、袴田氏の供述の任意性の確保に努める必要があったが、検察官が、袴田氏に警察の取調べ状況を尋ねるなどその実態把握に努めたことはうかがわれない」と分析。さらに担当検事が「警察と同じ心証を抱いて、袴田氏が犯人であると決め付けたかのような発言をしながら自白を求めていた」と判決に同調、「検察と警察は違う」と告げていても「供述の任意性が担保されたとはいい難い」と当然の評価をした。
5点の衣類のズボンのタグに記された「B」の意味を巡っても、報告書は「確定審での検察官の立証には不十分な面があった」とした。「B」は確定控訴審判決で「サイズ」を表すと認定され、実験でズボンを履けなかった巖さんが事件当時は着用できた根拠とされたが、その段階で「色」を示す記号だとする業者の供述調書が存在したことについて、第2次再審請求審まで検察がこの事実誤認を見逃していたとして「審理にも混乱を招いたことは否定できず」「訴訟活動として反省が求められる」とした。
しかし、確定審の検察官は弁論で「B」の意味を熱弁しているから「見逃していた」はずはない。この問題の本質は「証拠を隠したまま虚偽の弁論をして」誤判を導いた点にあり、「審理に混乱を招いた」程度のものではない。検証は事の重大さを認識しているとは言えない。
巖さんが1981年に再審を請求してから昨年の無罪判決までに43年以上を要したのは、検察の証拠開示が不十分だったことが大きな原因である。特に、5点の衣類の血痕の色への疑念を決定づけたカラー写真やネガについては、30枚の鮮明な写真が開示されたのが2010年。さらに「他にはない」としていたにも拘わらず2014年になって「新たに見つかった」として93枚のネガが追加開示されるなど、その対応への批判は根強い。
報告書は、第2次再審請求審の初期段階(2010年5月)に検察は「開示できる証拠は任意に開示する」との方針を明示したと強調、それ以降は「対応は概ね問題はなかった」と総括した。第1次再審請求審で証拠開示をしなかったことについては、弁護人の開示請求が抽象的だった、裁判所の命令・勧告がなかった、当時は証拠開示が制度化されていなかったとして、合理化した。
ただ、5点の衣類のカラー写真とネガについては、申立が十分であればという条件付きながら、第1次再審請求審で開示しても「プライバシー侵害などの弊害があったとは言い難い」として、その段階で積極的に探していれば「再審請求審の審理がより促進されていた可能性があった」と弁明、「一部の証拠の管理・把握が不十分であったために、結果として、提出する証拠に漏れが生じてしまっている」と落ち度を認めた。
審理の長期化については、最高裁の請求棄却決定までに約27年を費やした第1次請求審に問題があったとの見方を示し、三者協議に時間を要したことなどを挙げ、「積極的に審理を促進する方策が十分でなかったことが、手続の長期化の要因の1つ」と制度に責任を転嫁した。
第2次請求審については、5点の衣類の血痕を巡るDNA型と色合いに関して「専門的な内容にわたる検討」が必要だったとして「審理期間がある程度長期に及ぶこともやむを得ない面」があったとした。
検察が、2014年に静岡地裁が出した再審開始決定を不服として即時抗告したのは「科学的に誤った判断を是正するために必要かつ相当なもの」、再審公判で有罪立証をしたのは「関係証拠を総合評価すれば袴田氏の有罪を立証することができるとの判断の下」だったとして、いずれも正当化した。
しかし、そもそも最高裁差戻し決定の反対意見が「確定判決や第1次再審請求審では、5点の衣類が長期間みそ漬けされたことは当然視されたが、かかる推定の明確な根拠は示されなかった」と指摘していたこと、さらには「本件は被告人の自供を得なければ真相把握が困難な事件であった」という警察の総括や「他の証拠によって認められる本件の事実関係には、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない、あるいは、少なくとも説明が極めて困難である事実関係が含まれているとはいえ」ないとした無罪判決の評価を度外視しており、事件の本質に立ち返った検証とは程遠い。
5 冤罪事件の検証の在り方と記録の保存
やはり当事者による検証には限界がある。本件を検証することは司法制度そのものが問われている。また再審法の改正問題に直結するから、検証の主体としては立法機関たる国会がその国政調査権に基づいて特別調査委員会を設置して全面的・多角的な検証を試みることが必要である。
そして半世紀以上を費やした本件の記録は、今後の刑事司法に教訓を与える極めて重要なものであり、刑事確定訴訟記録法によって保存される。
再審無罪事件の確定記録の保存期間は、確定審が死刑や無期懲役だった事件であっても一般の無罪事件と同様に裁判書・保管記録ともに15年という運用となる。本件も、確定訴訟記録法に従えば、最低でも15年は保存されるものの15年が経過すれば裁判所不提出記録も含めて全て廃棄されてしまう可能性があり、これは社会の損失である。
他方、地検検事正の上申に基づいて法務大臣が「刑事参考記録」に指定すれば半永久的に保存される。そして日弁連支援事件で再審無罪を得た事件のうち最後に刑事参考記録に指定された事件は島田事件である。袴田事件はこれを凌駕すると言えるから、当然に刑事参考記録に指定すべきである。しかし未だに指定されていない。
(2025年11月05日公開)