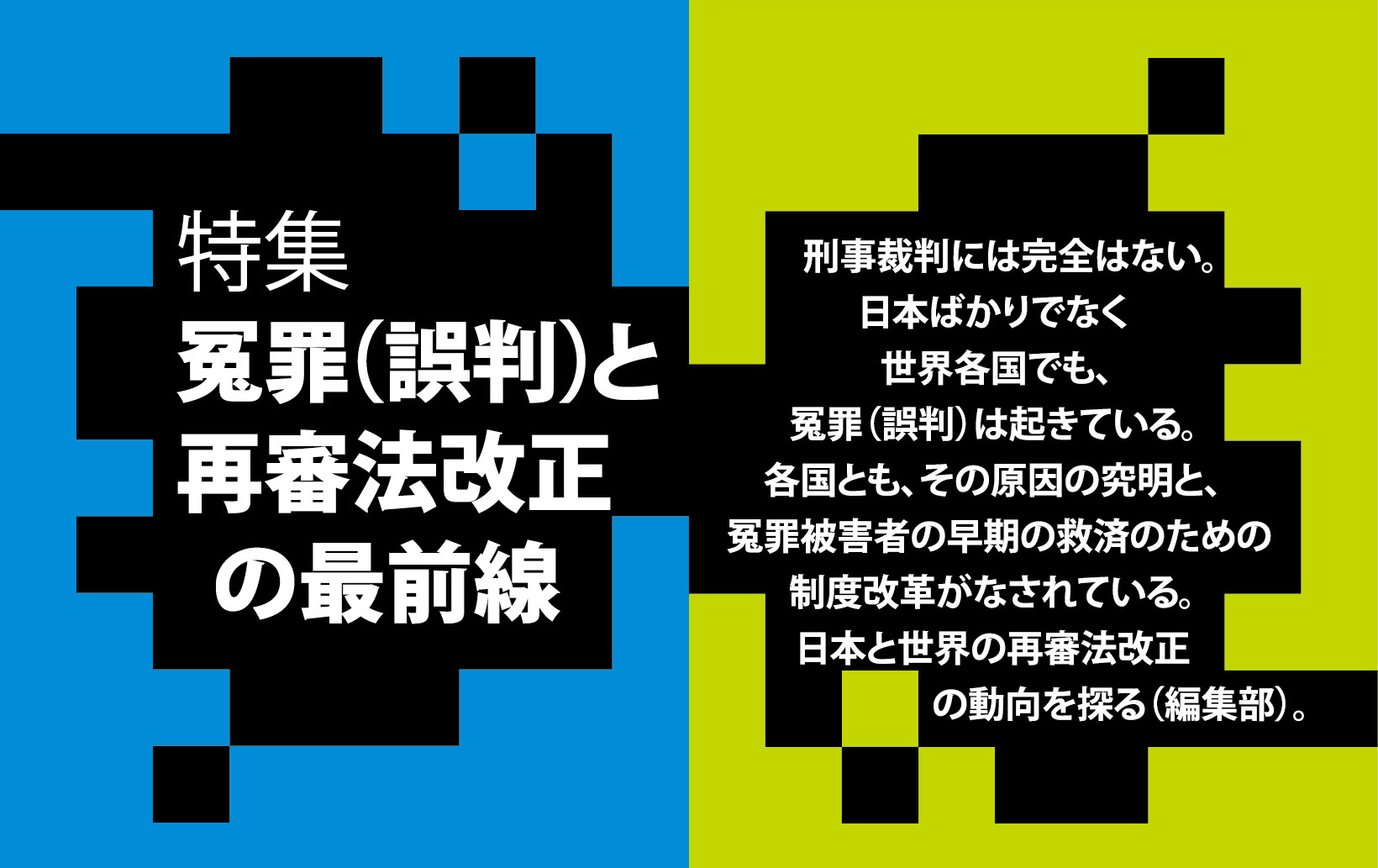1 再審制度の憲法的基礎——「誤判を免れる権利」
⑴ 本稿の目的
本稿は、現行制度の構造的問題がどこにあるかを明らかにしたうえで、請求人の再審請求権を実効的に保障するという観点から、制度改革の基本的視座を提示する。その前提として、再審請求権(刑訴435条)を保障することの意義を明らかにする。
⑵ 「誤判を免れる権利」と利益再審制度
日本国憲法が39条において二重の危険を禁止したことによって、旧法の不利益再審は廃止され、現行刑訴法は利益再審のみを規定することとなった。利益再審は、誤判の是正、それによる無辜の救済ための制度として純化され、それゆえ人権保障の制度となったとされた。
二重の危険の禁止は不利益再審を禁止するものではあっても、利益再審という制度を積極的に要請するものとはいえない。誤判の是正・無辜の救済のための利益再審を積極的に要請するものとして再審制度の基盤にあるのは、憲法上の権利としての「誤判を免れる権利」である。
自由な民主的社会において、何よりも尊い価値とされるべきは、人が皆、等しく「個人として尊重される」ことである。憲法13条が示すところである。人が皆、「個人として尊重される」のであれば、国が、正当な理由によることなく、人の生命はもちろん、自由、財産を奪うことは決して許されないはずである。誤判により人を有罪とし、刑罰を科すことは、国が、正当な理由なくして、人の生命、自由、財産を奪うことにほかならない。
ここにおいて、人が「個人として尊重される」ことに基づき、「誤判を免れる権利」が保障されるべきことになる。誤判を免れる権利は、通常手続において誤判を受けることがない権利とともに、誤判が確定した場合には、誤判の是正を求める権利という二つの局面を有する。前者は、黙秘権(憲38条1項)、証人審問権(憲37条2項)、弁護人の援助を受ける権利(憲34条・37条1項)、予断排除原則(憲38条1項、刑訴256条6項)、自白法則(憲38条2項、刑訴319条1項)、伝聞法則(刑訴320条1項)など、通常手続において誤判を回避するための様々な手続保障として具体化している。再審請求の局面で後者を具体化したものが、刑訴法の定める再審請求権にほかならない((誤判を免れる権利について、葛野尋之「再審請求中の死刑執行と再審請求手続」判例時報2465=2466号(2021年)135頁、同「再審請求中の死刑執行をめぐる法的問題」一橋法学21巻1号(2022年)6頁、村山浩昭=葛野尋之編『再審制度ってなんだ——袴田事件に学ぶ』(岩波書店、2024年)30頁参照。))。
2 再審制度改革の基本的視座
⑴ 現行制度の構造的問題
再審請求権の実効的保障という観点からすると、現行制度は大きな構造的問題を抱えている。再審請求にあたり、請求人は、再審請求の趣旨、再審の理由などを示した趣意書とともに、証拠の提出が求められ(刑訴規283条)、裁判所は、請求人の提出証拠について、新規性・明白性が認められるかを審理・判断することになるから、結局、請求人は、明白な新証拠の提出を求められることになる。請求人が、請求手続の過程において検察官の開示を受けることにより、あるいは検察官が裁判所に提出した証拠を閲覧・謄写することにより獲得できた証拠を新たに提出することができたとしても、裁判所は、新たな提出証拠について新規性・明白性が認められるかを審理・判断することになるから、請求人が新規・明白な証拠の提出を求められることに変わりはない。
現行制度の構造的問題とは、請求人が再審請求において明白な新証拠の提出という重い負担を課されているにもかかわらず、明白な新証拠を獲得することが著しく困難であるという点である((葛野尋之「誤判救済と再審制度——イギリス誤判救済制度からの示唆」判例時報2434号(2020年)154頁。ここにいう明白な新証拠を獲得することの困難性は、請求人が再審請求にあたり明白な新証拠を用意することができないということだけでなく、たとえば袴田事件の第2次請求におけるみそ漬け実験報告書に対する5点の衣類発見時のカラー写真およびそのネガの獲得のように、請求時に提出した証拠について裁判所が新規性・明白性を判断するための重要証拠の獲得が困難であることも含む。))。この構造的問題は、請求人が、通常手続において捜査機関が収集・作成したものの、裁判所に提出されなかった証拠(不提出証拠)に広くアクセスすることができないことから生じる。証拠アクセスが限定されているがゆえに、請求人は、再審請求において明白な新証拠を提出することにおいて、大きな困難に直面する。さらに請求後、請求手続の過程でも、請求人が新証拠の明白性について効果的な主張・立証を行うことも難しい。
通常手続が当事者主義をとるため、公判に提出される証拠の大部分は、検察官が被告人の有罪を立証するために請求する証拠である。さらに、検察官が開示する証拠は限られているうえに、開示証拠の多くも、裁判所には提出されることはない。こうして、捜査機関が収集・作成した証拠の多くが、不提出のままに終わる((斎藤司「再審請求審における証拠開示と立法」犯罪と刑罰31号(2022年)89頁は、そうであるがゆえに、請求審裁判所の手許にある証拠が限られており、積極的な事実の取調べを行うなどして、職権主義の請求手続において裁判所が再審理由の有無を判断するために果たすべき職責を全うすることができない現状があると指摘する。的を射た指摘である。))。
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年07月03日公開)