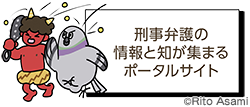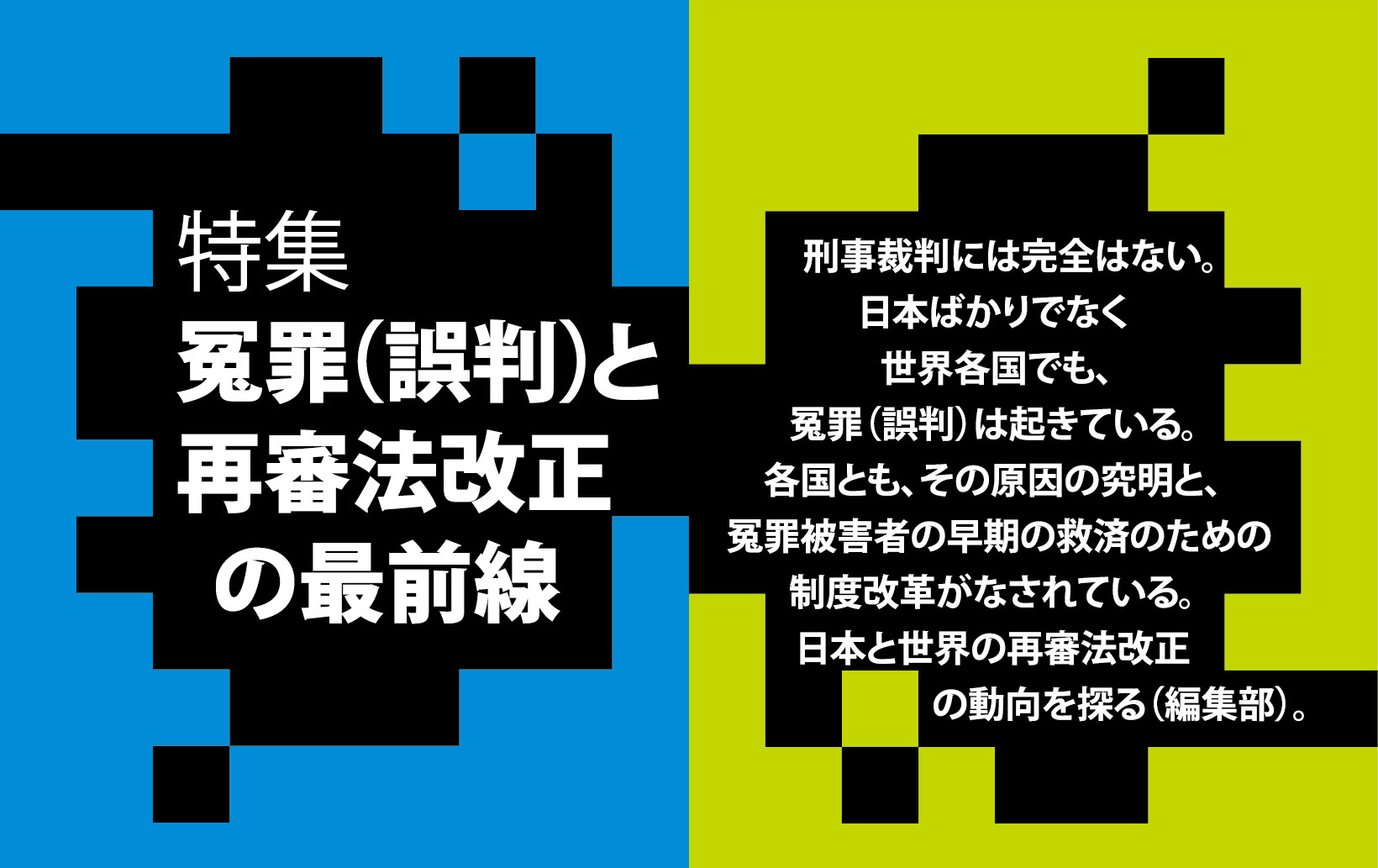1 はじめに
去る6月30日に開催された第3回会議のヒアリング終了後、筆者ら日弁連委員が、今後検討すべき追加の論点出しを行ったことについては、すでに本特集の第8回で述べた。これを受けた法務省は第4回会議に先立ち、再審部会で検討すべき論点を盛り込んだ、合計14項目にわたる「論点整理(案)」を委員に提示した 。
再審制度の見直しが法制審に諮問される前の2024年11月に、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」で法務省が提示した「『再審請求審における証拠開示等』論点整理(案)」は、全部で10項目だった 。法務省は、在り方協議会での論点整理案をベースに法制審での検討項目を決めるつもりだったと思われるが、今回提示された再審部会の「論点整理(案)」には、第3回会議で日弁連委員が追加すべきと主張した論点についてもほぼすべて網羅されていた。
この14項目の論点整理案について、再審部会の各委員・幹事から特に反対意見は出されなかった。先の通常国会で野党6党が提出した改正法案に掲げられた4項目については、議員立法で先んじて迅速に成立させ、残された多岐にわたる論点については、法制審で慎重な議論を経て抜本的な改正を実現させるべき、という日弁連の立場からも、追加を提案したものも含めて漏れなく論点が網羅されていること自体には異論はない。
ともあれ、2025年7月15日に開催された第4回会議から、いよいよ再審法改正の具体的項目についての議論が始まった。
以下、第4回会議における議事内容を速報する(執筆時点で議事録が公表されていないため、以下の内容は筆者の記憶による)。
2 部会資料をめぐる攻防
法制審議会─刑事法(再審関係)部会のサイトで「第4回会議」のページにアクセスすると、「配布資料」「委員提出資料」として多数のファイルがアップされている 。
このうち、「配布資料」というのは、事務当局(法務省)から委員・幹事に事前配布される資料で、第4回会議においては、上述の「論点整理(案)」と「諸外国の刑事再審に関する法制度(追補版)」がこれに該当する。後者の「諸外国の刑事再審に関する法制度」は、第1回会議の前に法務省から委員・幹事に配布されていたが、日弁連内部で検討したところ、その内容に不十分な点や誤解を招きかねない点が散見された。第1回会議の席上で筆者がその旨を発言したところ、大澤裕部会長から「具体的に問題点等があれば事務当局の方に御指摘いただいて、それをもとに扱いを詰めていく」との意向が示されたため、日弁連内で具体的な修正点をまとめ、法務省サイドに提示した。法務省による検討の結果、見解が異なるとして修正に応じない箇所もあったが、いくつかの点については日弁連側の指摘を受けて改訂した。これが第4回会議の「追補版」である。
他方、「委員提出資料」は、再審部会での議論にあたり参考となる資料を、各委員の側から提出するものである。第4回会議では筆者が、「諸外国の有罪確定後救済制度」と題する、日本、アメリカ、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、台湾の制度を各国につき1枚にまとめた表とその説明文、及び、21世紀に再審無罪が確定した7事件のうち、ヒアリングの対象となった袴田事件・東住吉事件以外の5事件(湖東事件、松橋事件、足利事件、東京電力女性社員殺害事件、布川事件)のそれぞれについて、事件の概要や再審手続における問題点をまとめた一覧表、そして、超党派議連が議員立法による改正案を作成するにあたり、日弁連から喫緊の改正項目を提示した「再審の請求の手続に関する刑事訴訟法の特例ならびに再審の手続のための記録及び証拠物の他の保管及び保存に関する法律案(「河井試案」)」を提出し、村山浩昭委員が日弁連の再審法改正意見書である「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を提出した。
また、最高裁刑事局長の平城文啓委員から、「令和6年度刑事専門研究会3(現代刑事法の諸問題2)共同研究『再審をめぐる諸問題』結果概要」と題する資料が提出された。これは、2025年2月18日に最高裁判所司法研修所で、現役裁判官48人が参加して、再審請求審の審理手続をめぐって直面するさまざまな問題について討議を行った内容を取りまとめたものである。
委員提出資料も会議期日前に法務省から各委員・幹事に配布され、第4回会議では、当日までに読み込んできていることを前提に、資料に対する質疑の時間が設けられた。質疑は筆者が提出した海外法制資料に集中し、成瀬剛幹事がアメリカとイギリスの制度について、川出敏裕委員がドイツの制度について、森本宏委員が韓国の制度について、記載の誤りや留意すべき点などを指摘した。この資料は、法務省側が配布した上述の「諸外国の刑事再審に関する法制度」では海外の法制度が正確に伝わらないと危惧した日弁連のバックアップメンバーである研究者たちの献身的な協力のもとで作成したものである。もとより記載の誤りについては真摯に受け止めて速やかに修正するが、見解の相違や指摘者側の認識の誤りと思われる箇所もあった。この点については、第5回以降の会議で補足説明を行う所存である。
配付資料をめぐっては、もう一悶着あった。6月18日に野党6党の共同提案によって国会に提出、法務委員会に付託され、継続審議となった「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」 (第217回国会衆法第61号)について、筆者は、議員立法による法案が正式に提出された以上、再審部会における議論の中でも言及することは確実であると考え、事務当局に対し、「配布資料」として委員・幹事に共有するよう要請した。
しかし、法務省は「配布資料」とすることは拒否し、「机上配付資料」とすると回答してきた。両者の違いは、前者が法制審の正式な資料としてHPにも掲載され、広く国民からのアクセスの対象になるのに対し、後者は会議当日、各委員・幹事席に置かれたタブレット型端末に格納される扱いに留まることである。立法府が法案として受理し、審議の対象としている法案を法制審の正式な資料にしないというのは、いかなる了見によるのか。その理由を問うと、「事務当局において責任をもって説明することができない内容だから」という不可解な回答だった。事務当局は会議の席上、「(法案の)内容は、衆議院HPでも公開されている。机上配布のものについて議論の対象にできないというものではないのでご理解いただきたい」と釈明したが、再審制度の見直しを多角的に検討することが求められる法制審であるはずなのに、ほかならぬ国会に提出されている法案を正式資料としない扱いについては、釈然としないものが残った。
3 論点ごとの検討
【議論の進め方】
第4回会議では、上記の「論点整理(案)」のうち、「1 再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写」の項目中、以下の4点を検討することとされた。
⑴ 再審請求審における閲覧・謄写に関する規律を設けるか
⑵ 再審請求審における検察官による証拠の一覧表の提出に関する規律を設けるか
⑶ 再審請求の準備段階における閲覧・謄写に関する規律を設けるか
⑷ 再審請求審において閲覧・謄写した証拠の目的外使用を禁止するか
このうち、⑴についてはさらに、①制度の枠組み(検察官が請求人・弁護人に証拠を直接開示する「直接開示型」か、検察官が公判不提出記録を裁判所に提出し、これを弁護人が閲覧・謄写する「裁判所提出型」か)、②具体的な規定の在り方、の二つに分けて検討することとし、⑵~⑷については、規律の必要性と具体的な規定の在り方を合わせて検討する、という進め方が示された。
その上で、大澤部会長から「できるだけ早期の答申が期待されており、まずはすべての論点を一巡回すことが重要」との認識が示され、その上で、項目ごとの検討時間につき20分ないし25分を目安とすること、各構成員らの発言について、できる限り2分以内に意見をまとめてほしいとの要望があった。
議論の具体的な内容については、次回から報告する。
*本著作物を、複写・印刷・転載・翻訳・頒布する場合は、こちらから事前に著作権者の許可を受けてください。
【関連記事:特集「冤罪(誤判)と再審法改正の最前線」】
・第11回「法制審議会─刑事法(再審関係)部会のリアル④——第4回会議(7月15日)[その2]」(鴨志田祐美)
・第9回「再審における証拠開示の理論的構造]」(斎藤司)
・第3回「再審法改正が実りあるものになるように(連載の趣旨)——再審制度を機能強化するための3つの課題①」(田淵浩二)
・第1回「カナダにおける再審制度の改革(上)──誤判原因調査から救済制度の新設へ」(指宿信)
(2025年08月01日公開)