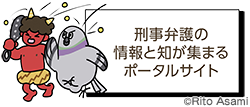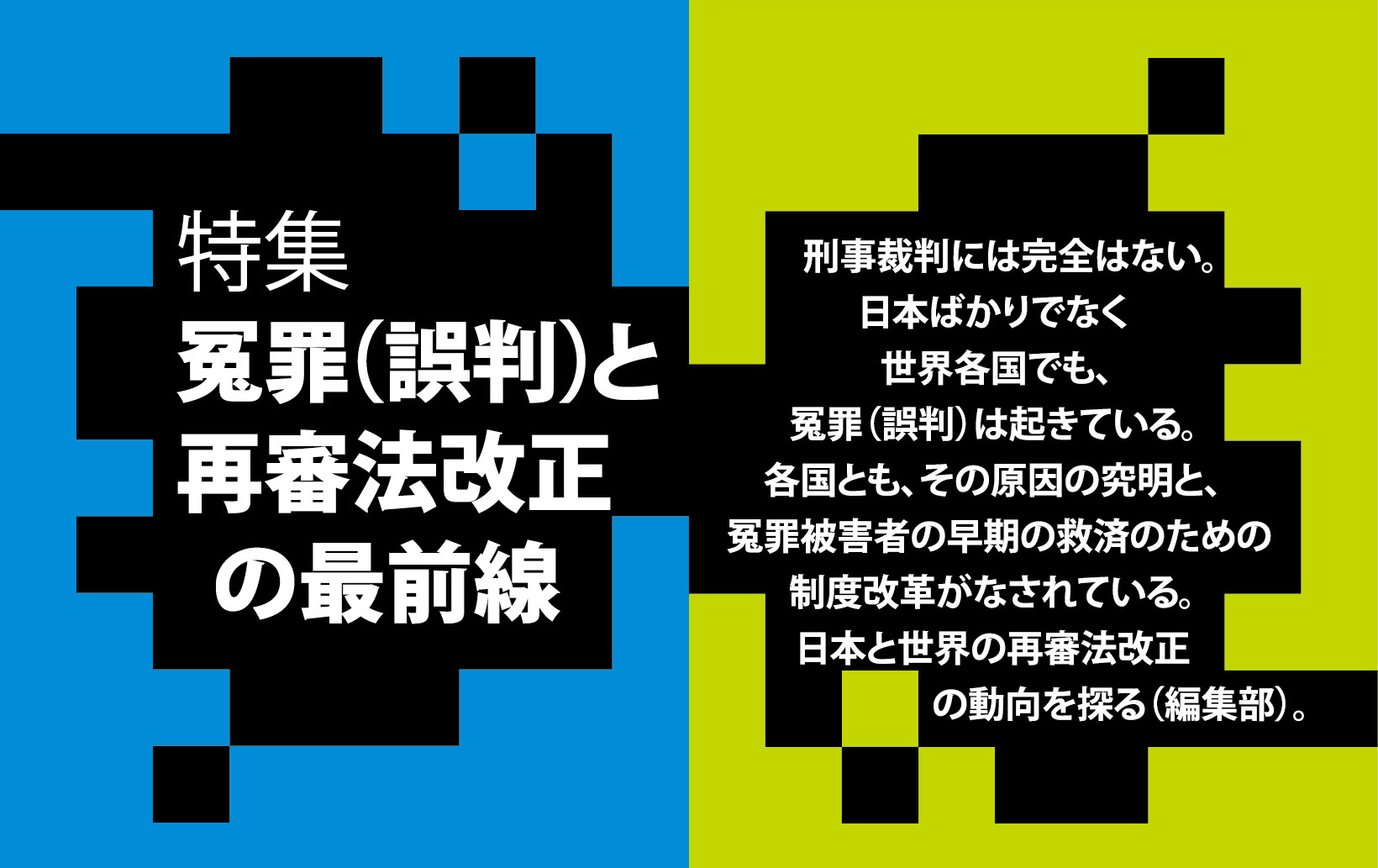1 はじめに
法制審議会―刑事法(再審関係)部会(以下、「再審部会」)の第5回会議は、2025年8月7日に開催された。これまでの会議が午前9時半から約2時間の開催だったのに対し、第5回会議は午後2時から午後5時までの3時間枠が設定された。
事務当局からは、論点整理案の「1 再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写」のうち、前回の続きである「⑸裁判所不提出記録・証拠物の保存・管理に関する規律を設けるか」、「⑹証拠物の証拠価値の保全・鑑定に関する規律を設けるか」、「2 再審開始決定に対する不服申立て」、「3 再審請求審における裁判官の除斥・忌避」、さらに「4 再審開始事由」のうち「⑴刑事訴訟法第435条第6号の規定を改めるか」までの5項目を議論する予定であるので準備されたい旨、事前に通知されていた。
日弁連の委員・幹事は、「再審事由に関する項目は、手続に関する規定と異なり、再審制度の根幹をなす部分であるから、無理やり詰め込むような形で第5回会議での検討項目に入れるべきでない」と主張したが、事務当局の方針を変更されることはなかった。
当日の議論では、後述するとおり、特に「再審開始決定に対する不服申立て」の議論に時間を要したため、結局のところ第5回会議は「再審請求審における裁判官の除斥・忌避」までの検討で終わった。
なお、法務省の人事異動により、今回から一部の委員・幹事に変動があり、森本宏氏(法務省刑事局長)が法務事務次官に就任したため、後任の刑事局長となった佐藤淳氏が委員となった。また、法務省参事官の中野浩一氏が東京地検に異動となった関係で、法務省刑事局刑事法制企画官の今井誠氏が再審部会の幹事に就任した。
以下、第5回会議における議事内容を詳報する。
2 部会資料をめぐる攻防
第4回に引き続き、今回も部会資料をめぐる若干の攻防が展開された。
まず、法制審議会─刑事法(再審関係)部会のサイトの「第5回会議」のページにアップされている資料から紹介する。
事務当局から「配布資料」として提出されたのは、「本人等の再審請求に基づく再審開始決定に対する検察官の不服申立て状況等」と題する一覧表(配付資料6)で、元被告人の側から申し立てられた再審請求に対し、開始決定がされた11件について、審理期間や検察官抗告の有無、抗告の結果などがまとめられたものである。なお、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」にも同様の資料が配布されており、今回は二つの事件(10番と11番)を追加している。
一覧表には事件ごとに番号が振られているが、事件名は罪名での記載のため、一見するだけではどの事件かが分かりにくい。解読すると1番は袴田事件(第2次)、3番は湖東記念病院事件(第2次)、4番は松橋事件、6番と7番は大崎事件(第3次)、9番は日野町事件(第2次)、11番は福井女子中学生殺人事件(第2次)である。また、2番と5番の事件は、第3回会議のヒアリングで田辺参考人が言及した事例であり、事案の概要については同参考人の提出資料に記載がある(第3回田辺委員提出資料)。
再審開始決定に対して検察官が抗告した事例はほかにもたくさんあるのに、なぜ、これらの11件のみが抽出されたのか。この資料の脚注には、「本資料は、法務省刑事局において保管中の行政文書に基づき作成したものである」との記載があるが、他の事件も公刊されている判例集などで容易に情報収集できるはずではないか。一覧表記載の事件数を絞ったことで、一見すると、検察官が抗告を行った事件の半数が「再審開始せず」となっているようにも見えてしまう。これらの点については、会議の中で筆者が具体的に指摘したので後述する。
(2025年09月17日公開)