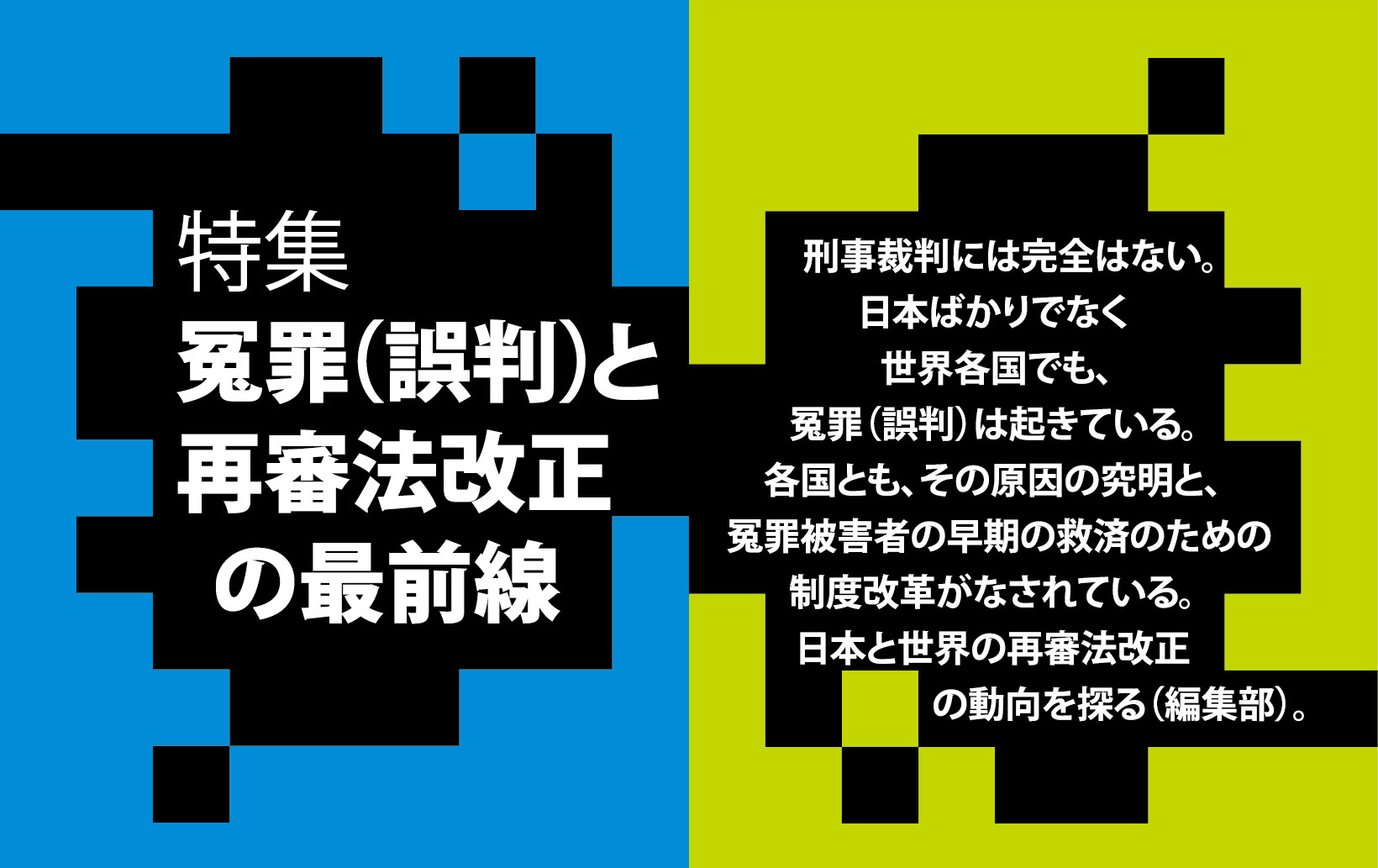7 2022年政府報告書
2019年12月、カナダ首相のトルドー氏が、司法大臣と検事総長に当てた公式書簡[1]を発信し、新たな再審請求審査機関を創設するよう指示した。これを受けて、2020年12月、司法大臣のデビッド・ラメッティ氏が次のように述べて、カナダにおいて再審請求審査のための独立した機関の設置に向けて政府が動き出すことを明らかにした。すなわち、「独立した(再審)審査委員会の創設は、カナダで議論されている誤判を(救済する道を)根本的に変えることになるだろう。これによって、(再審開始という)司法大臣の最終権限が、政府から完全に距離を置いた、政治的に中立の独立した機関へと移譲されることになる」と。
⑴ 報告書の概要
パンデミック期におこなわれた調査に2年が費やされ、2022年2月、カナダにおける独立した再審請求審査機関の設置を求める政府報告書が公表された[2]。司法大臣からの委嘱を受けて検討されていたものである。調査にあたっては、誤判冤罪当事者、各国のCCRCや同種制度の関係者、教育関係者、研究者、弁護士、誤判原因調査委員会関係者、犯罪被害者団体、現在の再審請求審査にあたっている司法省再審審査委員会関係者など200を超える多数のインタビュー(オンライン)が重ねられている。そこには17名の雪冤者も含まれていた。
報告書の起草にあたったのは、先住民問題に詳しいオンタリオ州出身のハリー・ラフォーム判事と、ケベック州で初めてアフリカ系カナダ人として裁判官に任命されたジュアタニア・ウェストモランド=トラオレ判事の2人である。報告書作成のための調査にあたったのはトロント大学の刑事法の専門家であるケント・ローチ教授、英国のバリスターで再審請求審査に明るいフェリシティ・ウィリアムズ氏、そして元検察官で弁護士のアイディーン・ラフォーム氏の3名である。
報告書は導入と結論を除くと13章からなり、ヒアリング参加者全氏名と意見書提出団体一覧が付けられ、200頁を超える大部である。各章のタイトルだけを紹介し、内容については報告書冒頭に置かれた要約と50に及ぶ勧告項目の重要な部分だけを紹介するに留めたい。
各章のタイトルは次のとおり。A.報告書のアプローチ、B.新たな審査委員会の特徴——独立性、予防的、組織的で十分な財政的基盤、C.現行の審査制度、D.新たな審査委員会の構造、E.新たな審査委員会の権能、F.請求人やイノセンス・プロジェクト、犯罪被害者等との関係、G.予備判定と暫定的釈放、H.証拠収集・証拠保全権限、I.審査結果の公表と司法審査、J.再審開始の負託と救済、K.上訴理由と証拠法、L.他の機関等と委員会の関係、M.(雪冤者の)社会復帰支援、である。以下ではこのうちB、D、E、H、Jを中心に紹介することになる。
⑵ 新たな委員会の性質
報告書はまず政府が取る方向性として3つの選択肢があると示した。第一は、個人の再審申立てに応じるだけの委員会制度の創設、第二は、政府から独立し十分な財政的基盤のある連邦政府に含まれる小規模の機関の創設、第三は、事実冤罪が証明されるか、誤判が明らかな場合に限って審査する委員会制度の創設である。
報告者らは、まず新たに設ける委員会が積極的かつ組織的性格を持つべきだとして、現行のような、冤罪者の代理人やイノセンス・プロジェクトなどの無償でおこなわれているサービスに基づいた請求を受けて審査するだけにとどまらない制度を提案した。すなわち、現行のカナダの審査制度を受け身的で消極的だとみなしており、それが再審開始の低い数値に現れているとする。特に報告書は現行制度で女性や先住民族、黒人といった人々の請求が認められにくい傾向があるとする。
したがって、新たな委員会制度では請求を受けてから審査するのではなく、積極的に潜在的な請求人にアプローチすべきだとしている。そうしたプロアクティブな再審審査機関の例として、スコットランドやニュージーランドのCCRCを挙げている[3]。
組織的働きの例としては、誤判の危険性に関する調査などを挙げている。そうした活動内容については諮問委員会を創設して意見を求めるべきだとする。
⑶ 新たな委員会の独立性
独立性に関しては、従来司法省の内部組織である有罪事件審査部門(CCRG)が持っていた再審開始付託権限を新たな審査委員会に移行させ、委員会が司法権からも行政権からも独立して事件を調査し、可能な限り自由な立場で審査が実施できるようにするとともに、決して“二級司法”に陥らないよう十分な財政的基盤を整えるべきとする。その財源は連邦裁判所の予算から支出されるものとし、新たな委員会は9人のメンバーで構成され、メンバーは終身雇用として地位と給与が保障されるものとすべきで、給与は連邦上級裁判所の判事と同等でなければならないと勧告する。
再審請求の対象事案は事実冤罪の事案だけでなく全ての誤判に関する事案を含むべきだとする。事実冤罪が重要なターゲットであることを認めつつ、財政的理由からそうした事案に救済対象を限定すべきだとしない立場をとる。これは量刑誤判のケースや責任能力が争われたケースも含めることを意味する。
⑷ 新たな委員会の名称と委員の選出
この報告書では、新たに創設される委員会の名称として他国で使われているCCRCを使う考え方もあるものの、カナダでは「誤判委員会(Miscarriage of Justice Commission)」とすべきだという提案をしたところが注目される。
9人のメンバー構成は、3分の1は法律家出身で、3分の1は誤判原因に精通した専門家、残りの3分の1は少数民族などの出身に配慮した構成とすべきと勧告した。刑事司法関係機関での勤務歴や、犯罪歴は欠格事由としない一方、利益衝突には配慮が必要だとしている。委員会の文化はオープンで協調性あるものでなければならず、効果的なコミュニケーションの確立や批判的な精神、審査手続やポリシーの監査の必要も指摘している。
委員会活動を支えるスタッフの整備も重要な課題で、法律家は当然、冤罪被害者や犯罪被害者の支援にあたった経歴が望ましく、調査能力が何より重視されるとした。またより高度な調査能力のある外部の専門家を雇用することも認めるべきだとする。
委員会の設置場所は首都オタワ以外の土地にすることが象徴的で望まれるとしたが、これは必須要件ではないとしている。本質的な問題は十分な財源と独立性の確保であり、何処に設置されようと再審請求人は東海岸から西海岸まで広い範囲に及ぶため、事案を調査するためには全国に行く必要があるとする。
⑸ 新たな委員会の請求手続と判断内容
請求手続に関しては、再審審査請求をおこなう者は弁護人依頼人特権を放棄するよう求められるとする。委員会は裁量に基づいて請求人に代理人を公費で付することができ、委員会の審査に協力させることができる。この段階でイノセンス・プロジェクトや代理人と協調することも必要とする。また、被害者のある犯罪の場合、犯罪被害者憲章(Canadian Victims Bill of Rights)に留意し、被害者の審査について告知する義務を負うとする。その内容と時期について委員会は裁量を持つ。
再審開始判断についての基準は法令で明確に固めるのではなく、スクリーニングポリシーを独自に持つ柔軟性を認めている。また、あらゆる人に対して証拠物の保全や整理を求める権限や宣誓供述を求める権限を委員会が持つことを勧告している。イングランド等のCCRCなどと同様に、あらゆる人や機関に対して(警察、検察、以前の弁護人など)法的に認められた特権や権限に関係なく、関連する証拠の提出を求めることができるとする。また、プライバシーの要請もこの権限の適用除外事由には当たらないとする。また、新たな委員会の下す否定的な結論に対する請求人の異議申立ても認めるよう提案し、その際には代理人の費用を保障すべきだと勧告する。
裁判所に対する再審開始の付託判断は、「誤判が発生した可能性(may)」で足りるとした。これは現行のCCRGで行われている水準よりも低い。CCRGでは「誤判が発生した蓋然性(likely)」を基準としていたからである。また、イングランドやカナダの現行CCRGが用いている、付託すれば裁判所によって確定判決が破棄されるとの“予想”を基準とする「予想テスト」も採用しなかった。CCRGとは異なる点として、新委員会は裁判所への上訴付託とするか再審付託とするかを選択できるとする。請求人が特に再審という救済を求める場合には上訴ではなく再審を選ぶ。付託の要件としては、上訴理由があることと、新しい証拠で許容されるものが存在することである。
付託を受けた裁判所は、委員会が検討し依拠した新証拠を必ず検討する義務があるとする。これは裁判官の証拠評価に関わる裁量を拘束するという意味でコモン・ローの世界では革新的な提案となっている。
⑹ まとめ
最後に、新たな委員会は再審請求の審査のみならず、刑事司法制度の問題や懲戒に関わって独自の調査権限を有しておくべきとも勧告されている。そして、冤罪被害者への賠償問題には委員会は関わるべきではなく、この点は立法によって解決されるべきとする。
注/用語解説 [ + ]
(2025年06月07日公開)