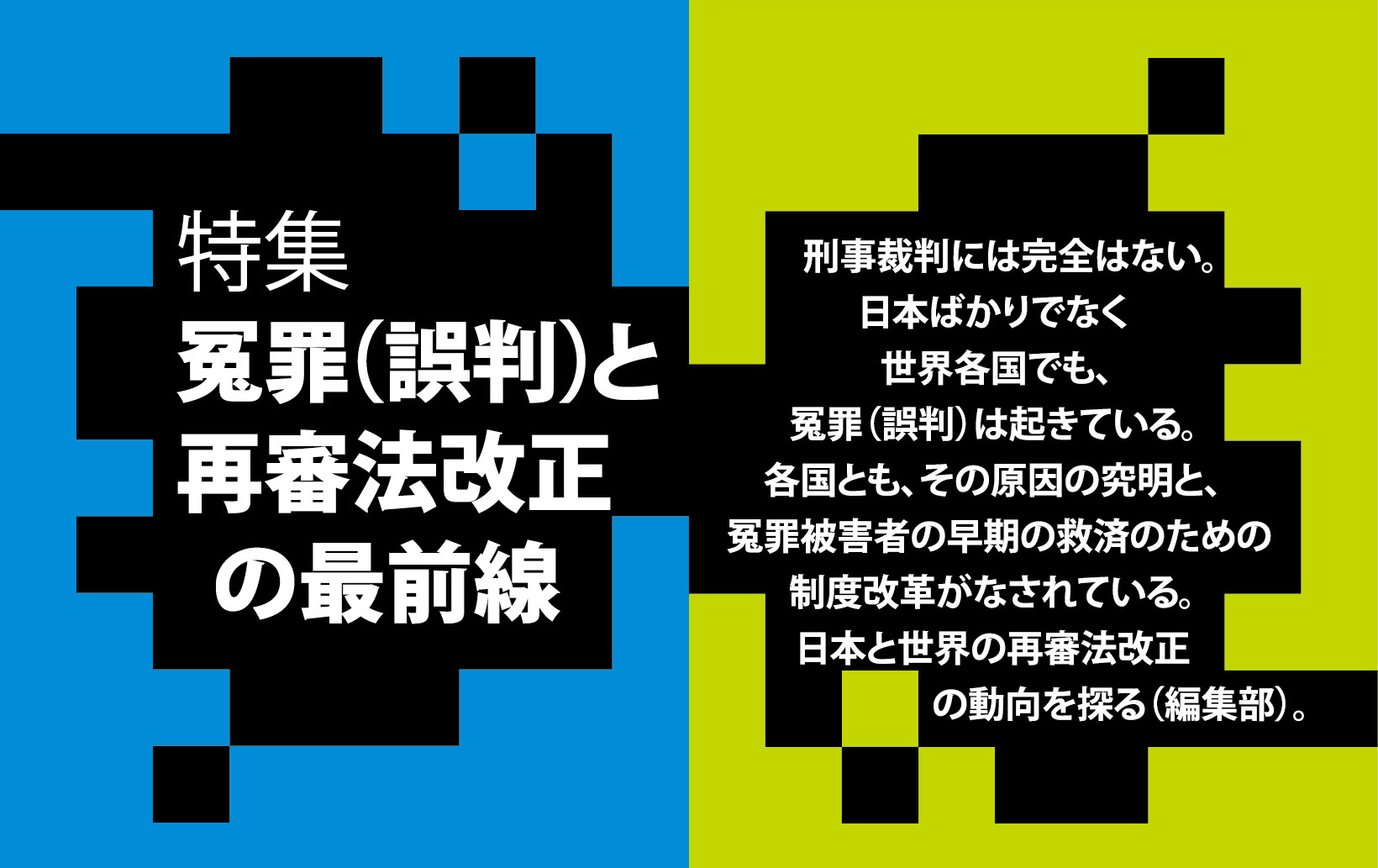1 はじめに
現在、「法制審議会—刑事法(再審関係)部会」(以下、「法制審」)で再審に関する法改正の議論が進行中である。また、再審法改正の実現を目指して国会内に設置された超党派議員連盟である「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」による改正案は、自民党内での慎重論が根強く意見がまとまらなかったこともあり、野党6党共同による「再審法改正案」提出という形になり、継続審議となった。
この再審法改正を巡る主要論点の1つが、いわゆる「再審請求審における証拠開示」である。この問題については、日本弁護士連合会「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」(2023年2月17日公表、同年7月13日改訂。以下、「日弁連意見書」)のように、裁判所による検察官保管証拠の一覧表の提出命令、一定類型の証拠と再審請求手続における請求人または弁護人の主張立証に関連する証拠の開示などの幅広い証拠開示を主張する意見に対し、後述のとおり慎重な意見も見られる。「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示……について検討を行うものとする」との2016年刑訴法改正に関する附則9条3項を受け、同改正後の制度・運用における検討課題を整理するために開催されている法務省「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」(以下、「在り方協議会」)などで示される見解などである。
これらの証拠開示をめぐる議論では、「職権主義」など複数のキーフレーズが示され、そこから証拠開示の当否だけでなく、一定の証拠開示像も導かれている。そこで本稿では、上記の議論、特に慎重論を検討対象としながら、同様のキーフレーズを用いながら、他の証拠開示像を導くことはできないのか、できるとしてどのような制度がありうるかを検討する。
2 再審請求審の位置づけ・構造と証拠開示
一般的に、再審請求審は「職権主義」構造をとるとされる。そのため、当事者主義構造をとる通常審との違いが強調され、通常審の公判前整理手続の証拠開示に関する規定を適用・準用することはできないとの主張がなされている。そして、再審請求人が検察官に対し証拠開示を請求する権利に関する法的根拠は存在せず、さらに、裁判所が、検察官に対して証拠開示を命じることはできないとも主張されている((丸山哲巳「再審における証拠開示についての若干の覚書」秋吉淳一郎ほか編『これからの刑事司法の在り方〔池田修先生・前田雅英先生退職記念論文集〕』(弘文堂、2020年)217頁以下。さらに、福島弘『再審制度の研究』(中央大学出版部、2015年)54頁以下、濱克彦「再審——検察の立場から」三井誠ほか編『刑事手続の新展開(下)』(成文堂、2017年)634頁以下。))。
この見解の1つは、次のように主張する。「裁判所は、再審事由の有無を判断するために、検察官(または捜査機関)が保持している証拠を検討する必要性が生じる場合がある。そのような場合、裁判所は、事実の取調べの一環として、検察官に対し、当該証拠を裁判所に開示することを勧告することができると解される。この場合、検察官が証拠を開示する相手方は、前記のとおり再審が職権主義を基調としていることを考えると、再審を担当する裁判所ということになろう」と((丸山・前掲注1論文217頁以下。))。そして、この開示勧告を受けた検察官は、「公益の代表者」(検察庁法4条)として、証拠隠滅や関係者のプライバシー侵害などの弊害を疎明しない限り、これに応じる義務があるとする。
この開示勧告の条件としては、「①新規性があるか、少なくとも新規性が認められる可能性が提出されていること」、「②提出された証拠の明白性が認められる可能性があること」、そして「③明白性の判断を行う上で検察官(捜査官)手持ちの証拠を踏まえた検討が必要であること」が挙げられる。このうち、②については限定的再評価説を前提に、新証拠と有機的に関連する有罪認定の証拠の一部の証明力を減殺するにとどまり、有罪認定そのものに合理的な疑いを生じさせないことが明らかなときは、③が認められないので開示勧告はできないとされる((丸山・前掲注1論文218頁以下。))。この見解は、職権主義を根拠として、再審請求審による証拠開示勧告を主張するものである。
再審請求審の審判対象が再審事由の有無であることも証拠開示に関する根拠して挙げられる。「在り方協議会」では、次のような発言がある。
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年07月24日公開)