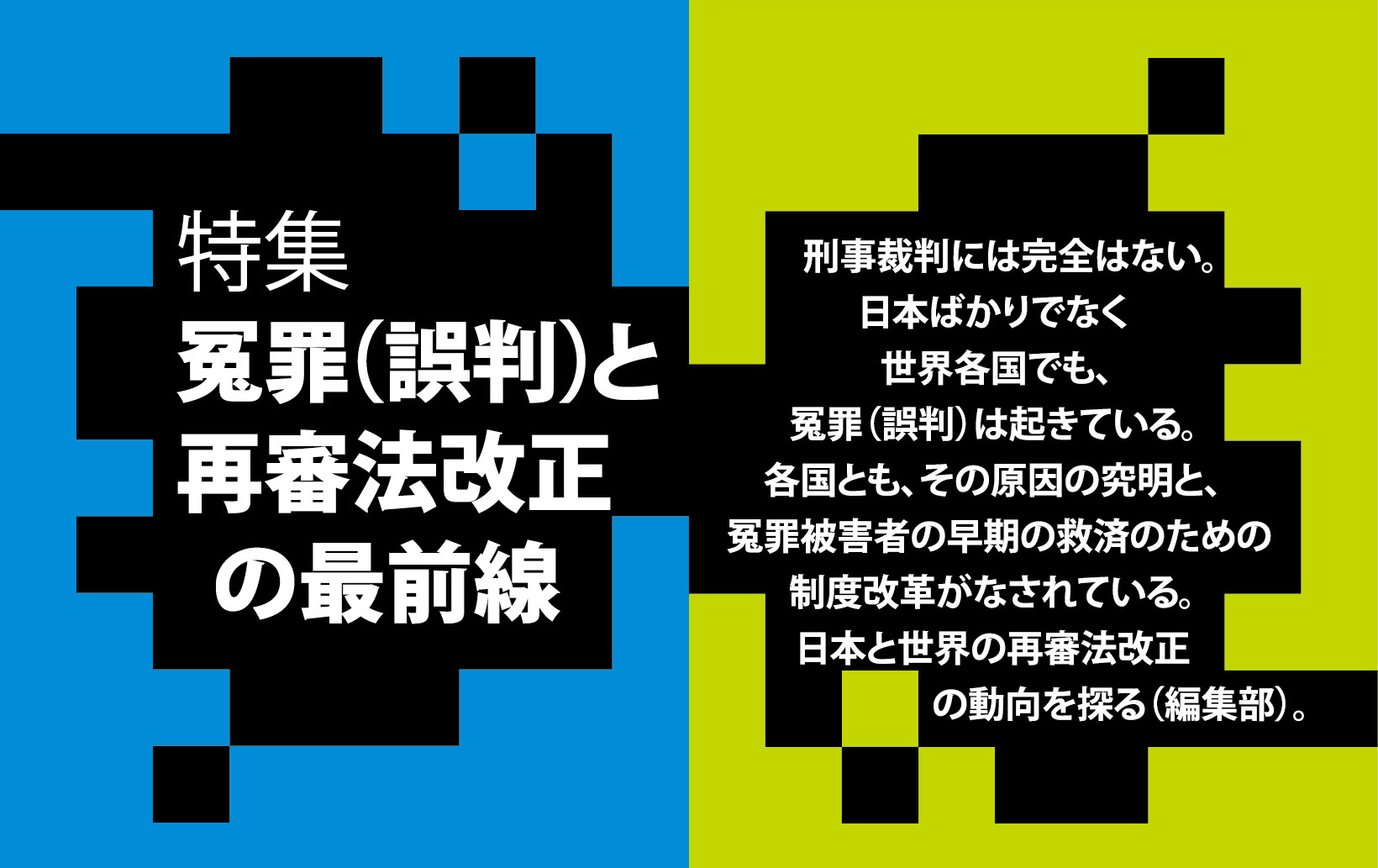3 中川博之氏からのヒアリング
中川博之氏は26年ほどの刑事裁判官のキャリアを経て、2019年に大阪家裁所長を最後に退官、京都大学大学院法学研究科の教授を経て、現在同大学院の非常勤講師を務める。ハンナン事件(証拠隠滅の主犯格とされた被告人が上訴審で無罪となり確定したことから、上訴せず先に有罪が確定していた「共犯者」が申し立てた再審請求事件)で再審開始決定をした経験をもつ。
ヒアリングにおける中川氏の意見の概要は以下のとおりである。
【再審請求事件の傾向について】
・再審請求事件の内容においては非常に様々なものがある。日本弁護士連合会が支援するような事件もあるが、刑事訴訟法第435条に定める再審の理由がないことが明らかな事件とか、刑事訴訟規則第285条で定められている判決の原本とか証拠書類等の添付がないものが非常に多く、また、同一の理由に基づく繰り返しの請求というようなものが多い。それらの事件の大半は短い期間で棄却の判断に至っている。
【再審請求事件における審理の実情について】
・再審請求書と確定判決を照らし合わせて読み、事案の争点の把握に努める。並行して検察官に求意見をし、確定記録、更に先行する再審請求の記録があれば、それらの記録も借り出しておくのが一般的。
・事実上の打合せは頻繁に行われている。弁護人から打合せの申出があった場合には、普通は応じていることが多く、その際、検察官に出席の有無を確認するのが一般的と思われる。打合せをどの時点で行うかについては、事案に応じて裁判官が個別に判断している。
・古い事件に関しては、証拠の量が多かったり、捜査記録が手書きだったりするために苦労する。また、昔の判決書はなかなか読み解けないものもあり、証拠の重さともあいまって、確定判決の構造の分析とか、再審開始の要件を判断するに当たってどこがポイントになるのかというようなことについて、見極めに時間を要する。
【再審請求審における裁判所の事実の取調べについて】
・請求審における事実の取調べについては、請求人が主張する再審事由と新証拠を出発点とし、新証拠が攻撃目標としている旧証拠に及ぼす影響の有無・程度を起点として判断するために必要な限度で行う。証拠書類・書証については原則として全て取り調べる一方、人証・証人尋問等については、その時点までの具体的状況を踏まえて柔軟に対応している。
【再審請求審における証拠開示について】
・裁判官が請求人の主張する再審理由の有無を判断するために、証拠開示を勧告ないし命令すべきと判断するための判断枠組みが、理論的な根拠のある明確なものになっていることが重要。
・手元にある証拠だけでは新証拠の明白性を判断することができないとき、請求人が主張する再審事由と新証拠を出発点として、当該事由の有無と、それが旧証拠に及ぼす影響の程度について判断をするために必要な範囲で追加の事実取調べを検討し、その事実取調べの対象となる証拠が不提出記録の中に存在する蓋然性があると思われる場合に、初めて証拠開示の要否を検討するというのが自然な発想。したがって、証拠開示は新証拠とそれに関連する請求人の主張との関係で必要な範囲に限定されるべき。
・再審における新証拠との関連で類型証拠というようなものを想定することは可能だが、その範囲に関しては、新証拠に基づく請求人の主張との関係で開示が必要となる証拠、これを主張関連証拠というのであれば、その範囲と実質的に異ならない。
・新証拠を離れて、確定判決を支える証拠との関係での類型証拠の開示は再審請求審の構造にそぐわない。証拠開示の範囲が広すぎると、再審請求審の出発点である新証拠と無関係に争点が拡大し、再審請求審が肥大化、第四審化するというふうな懸念にもつながる。
【あるべき法改正】
・再審請求において裁判官は、これまで限られた手続規定しかない中で運用を積み重ねてきたが、その背景には職権主義で行われている審理構造の問題とか、審判対象に対する刑事訴訟法上の基本的な考え方がある。今後、新たな条文が付け加えられることになったとしても、刑事訴訟法上の基本的な考え方と整合的なものにならなければ、裁判官が解釈に迷って、従前よりも運用が不安定になり、長期化するという懸念もある。
・刑事訴訟法第435条に関しても第6号に関する議論が中心となっているが、それ以外の各号の再審理由との整合性も保つ必要あり。
4 磯谷富美子氏からのヒアリング
磯谷(いそがい)氏は、31歳の女性が3人の男性に殺害され金品を奪われた強盗殺人事件(いわゆる「名古屋闇サイト殺人事件」(2007年)の被害者遺族(母親)である。3人の男性のうち1人は死刑が確定(すでに執行)、他の2人は無期懲役刑が確定した(このうち1人は判決確定後に別の強盗殺人事件等の犯人であることが発覚し、その事件で死刑判決が確定)。ヒアリングにおける磯谷氏の発言の概要は以下のとおり。
・娘の事件ではえん罪の可能性がゼロの犯人が捕まったために、真犯人ではない場合を想像したことはないが、もしえん罪の可能性があるということで再審が開始されたら、裁判当時と同じように闘うことはできない。
・判決に納得がいかなくて被害者側にも再審請求のような道はないのかと思ったが、何もなかった。
・再審が決まったら早く結審して、えん罪だった場合は真犯人逮捕へと踏み出してほしい。そのための証拠開示は必要だが、通常審の公判前整理手続で必要な証拠はすべて開示されているのではないのか。再審請求されたからといって全ての証拠を開示することになると、そうしなかった最初の裁判は何だったのかと裁判に対する不信感が出てしまう。
・プライバシーに関わるような証拠や名誉を毀損する証拠は開示すべきではない。娘が性被害に遭っていたとしたら絶対に証拠を開示してほしくないと思う。
・加害者同様に被害者側にも国選の弁護士を付けてほしいと願っていたので、有罪となった者が再審請求すれば国選の弁護人が付くというのは、破格の優遇ではないか。
・明らかに不当な再審開始決定があっても、被害者にはそれを争うすべがない。今後も不当な再審開始決定があった場合は、それを是正する制度は当然必要。安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになり、司法全体に対する信頼性が薄らぐ。
・真犯人に間違いなければ再審請求は受け付けないとはっきり定めてほしい。死刑判決を受けた者が執行を遅らせる目的で何度も再審請求をするという話も聞いている。死刑執行によって一つの区切りを付けて、前を向いて歩いていく遺族のことも考慮してほしい。
・一番の要望は、再審請求する必要がないように、三審制の中できちんと裁いてほしいということ。再審請求に関する法案より先に、どうしたらえん罪を生まないかを考えるべき。えん罪は犯罪の内容にかかわらず、あってはならない。どのような原因で間違ってしまったのかを振り返り、教訓にする必要がある。事件発生当時に関わる警察官の対応がとても重要であり、圧力や焦りや見込み捜査、作られたストーリーにこだわることのない、証拠に基づいた捜査が大切だと思う。
・再審請求者イコールえん罪者という視点でスタートするのは大変危険。えん罪で得する者は、本当に裁かれるはずであった真犯人だけ。被害者も、無実の罪を着せられた者も、共に被害者である。
(2025年07月12日公開)