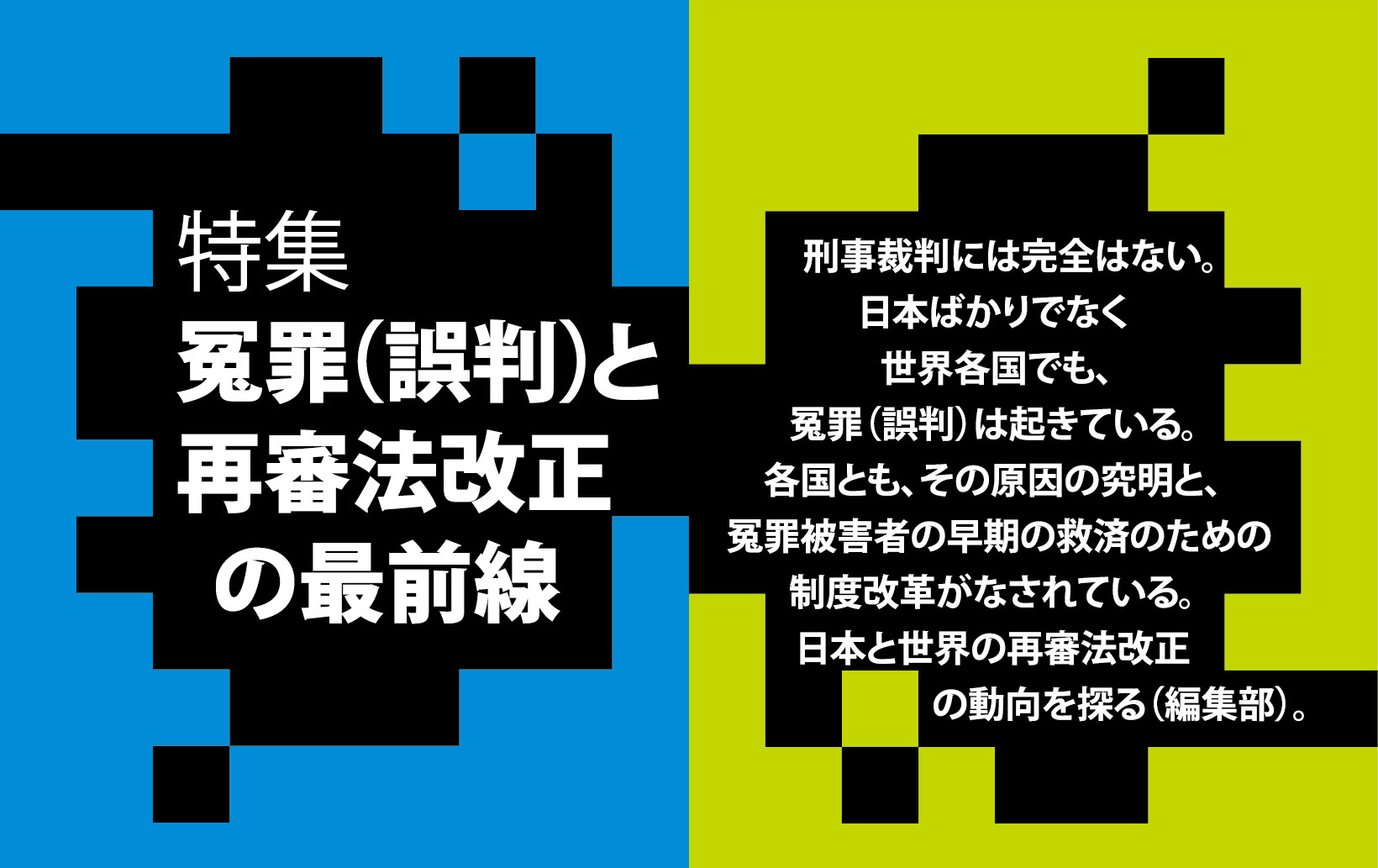5 髙橋正人氏からのヒアリング
髙橋弁護士は犯罪支援者団体「旧・あすの会」の元副代表理事で、同団体の代表理事だった故・岡村勲弁護士の随行として法制審等の会議に出席、被害者参加制度の3年後見直しに関する意見交換会では委員を務めた経験をもつ。
ヒアリングにおける髙橋弁護士の発言の概要は以下のとおり[1]。
・加害者のえん罪ばかりが報道され、被害者の視点が全く見落とされていることに気づいてほしいということ、人は誰でも間違いを犯すということを前提に制度を作らなければならないということの二つを述べるためにヒアリングを引き受けた。
・証拠開示規定を設けることには賛成である。30年たったら、殺人事件以外ではもう全て時効が成立し、時効が廃止された殺人事件でも、事実上、証拠は散逸してしまって真犯人は捕まらない。被害者の立場としても証拠は早く開示していただきたい。
・証拠の開示についてはもちろん検察官に大きな責任があると思うが、裁判所もしっかり証拠を採用し、弁護人も科学的な見識を高めることも大切ではないか。
・証拠の開示のうち、性被害に関する証拠については大反対である。性被害の女性からすれば、性被害の画像が世の中に存在していること自体が苦痛であり、それを再審に向けて保存するということなれば、せっかく性的な画像を消去・破棄できるようにした法改正の趣旨がないがしろになる。
・検察官の抗告の禁止について。憲法上は最高裁と下級審が一つあればいい、二審制で合憲であるところ法律で三審制にしているのは、人は間違いを犯すからである。人は間違いを犯すということの原点に戻ったときに、抗告を禁止するのはいかがなものか。
・再審開始決定をさっさとやれば、そして次の再審の手続でやれば、時間的な短縮になるという批判を受けたことがあるが、時間の短縮を言うのであれば、弁護人の不服申立権こそ禁止すべき。再審請求はほとんどが意味のない濫訴。それに対して弁護人が不服申立てをして永遠に続く一方、検察官は不服申立てができないという立場に置かれたとき、被害者はどう考えたらいいのか。
・日弁連が出した資料によれば17件のうち12件で再審開始決定が確定し、1件はまだ係属中、4件は不服申立てが認められている。もし不服申立権を認めなければ、この4件については「逆えん罪」ということになる。もし不服申立権を禁止したら、この4件については、被害者は「実は真犯人なのだけれども真犯人ではないことになってしまいました」と墓前に報告しなければいけなくなってしまう。こんな不合理なことが認められていいのか。不服申立権の検察官だけの片面的な禁止については大反対である。
・裁判官の除斥・忌避については賛成する。
・再審開始要件の緩和について「事実誤認があると疑うに足りる証拠」があればいいというのであれば濫訴になる。罰金刑になった交通事故の違反者でも再審請求ができることになってしまう。日弁連の言うとおり全て国選弁護人が就くことになれば、自分はお金を出さなくて済むのだから罰金刑になった人もどんどん再審を申し立てるだろう。また、不服申立てをする人というのは大概、不合理な理由で、例えば死刑執行を免れたいために、先延ばししたいためにするのがほとんどである。単に事実誤認があると疑うに足りる証拠だけで再審ができるのであれば第一審、第二審、第三審は何だったのか。罪を犯したことについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度について3回しっかりと審理したはずであり、それと事実上変わらない要件を設けるということは、四審制、五審制、六審制、七審制、永遠審になる。被害者は死ぬまで前を向くことができない。こんなバランスを欠いた制度はいかがなものか。
・死刑事件における再審請求手続中の義務的執行停止は、結局のところ死刑制度の事実上の廃止と同じことではないか。死刑制度反対論者の意見を取り入れているのではないか。
・えん罪というのは、もちろん今までの検察官にも問題があったと思うが、決してそれだけではなく、法曹三者全員の責任。それぞれが証拠を開示して、それを制することなく全ての証拠を見て、そして弁護人がしっかりとした見識と知識を持って反論する、そういうことをしっかりと通常審でやってこそ、司法に対する信頼が生まれるのではないか。
6 ヒアリングを踏まえた論点出し
ヒアリング終了後、部会長が、ヒアリングの結果も踏まえて今後検討の対象となる論点として追加すべきと考えるものについて、委員・幹事に意見を求めた。これに対し、日弁連推薦委員・幹事4名から追加の論点が提案された。
以下、それぞれの委員・幹事が提案した追加すべき論点について、箇条書きで記載する。
【田岡幹事】
・証拠開示(裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写)について
① 再審請求準備段階(再審請求手続外)における裁判所不提出記録(証拠品を含む)の閲覧・謄写を認める規定
② 再審請求の審理において、裁判所不提出記録(証拠品を含む)を提出させたり、証拠の一覧表(送致目録など)を提示させたりする権限、義務を裁判所に付与する規定
③ DNA鑑定が問題となる場合における証拠価値を保全するための保管・保存、鑑定の実施等の権限を裁判所に付与する規定
④ 証拠の取調べの前提として、裁判所不提出記録・証拠品の保管・保存に関する規定
・国選弁護人制度及びこれに関連する制度
① 再審請求審、及びその準備段階における国選弁護人制度の創設
② 再審請求人、再審請求をしようとする者が、弁護人、または弁護人になろうとする者と接見する場合の秘密交通権の保障に関する規定
③ 再審請求手続における弁護人の費用を費用補償の対象とする旨の規定
【鴨志田委員】
・再審公判の審理、とりわけ証拠調べに関する規律の在り方
・管轄裁判所(確定判決をした裁判所が高裁、最高裁の場合、再審請求審を地裁の管轄とすることができるか)
・再審請求権者の拡大、請求人死亡の場合の受継の規定
・再審事由について
① 435条6号の文言
② 死刑事件についての量刑再審
③ 原判決の手続に重大な憲法違反があった場合
④ 確定判決に代わる証明があった場合
・刑の執行停止について
① 死刑事件について再審請求がされた場合における必要的刑の執行停止
② 再審開始決定に伴う必要的刑の執行停止(死刑事件における拘置の執行停止を含む)
・不服申立期間の延長(再審開始決定に対する検察官抗告の禁止が前提)
【村山委員】
・再審請求手続期日の指定に関する規定
・再審請求理由について意見を陳述する機会を保障する規定
・再審請求人、弁護人に事実の取調べ請求権、DNA鑑定等の実施を求める請求権を保障する規定
・審理の終結日、決定日の告知に関する規定
・審理の公開に関する規定
【山本委員】
・開示証拠の目的外使用の禁止に関する規定
・再審請求審、再審公判への被害者参加に関する規定
・再審請求段階における被害者通知制度について
注/用語解説 [ + ]
(2025年07月12日公開)