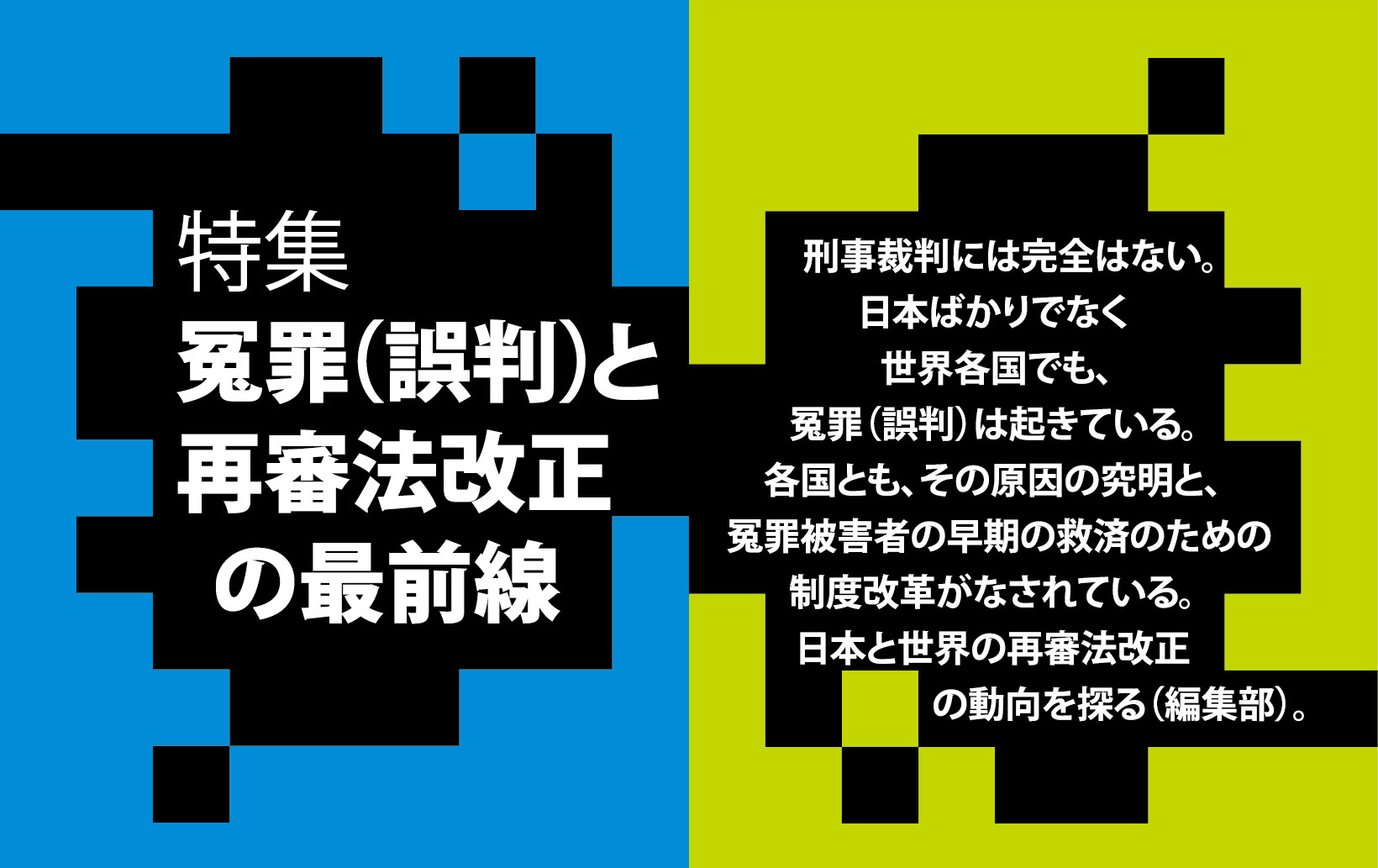7 第3回会議を振り返って
本特集では、再審部会のリアルを迅速に伝えることを優先すべきと心得ているが、最後に数点、筆者の受け止めを述べておきたい。
まず、田辺氏が「誤った再審開始決定が最高裁判所で是正された事例」として挙げた二つの判例(最決平29・3・31裁判所時報1673号127頁と最決平29・12・25判タ1454号40頁)についてである。田辺氏は検察官による抗告の必要性を示す立法事実としてこれらの判例を挙げていると思われるが、この二つの事例は同じ構成の最高裁第一小法廷による決定(なお、これまでに再審開始決定を最高裁が取り消したケースは、第一小法廷のほかには存在しない)である。いずれも比較的軽微な事案で、新供述(前者は被害者、後者は共犯者)を新証拠とする再審請求であり、請求審で棄却された後、即時抗告審で逆転再審開始となったという共通点がある。要するに、両事例とも再審請求事件としては特異なケースであり、これを検察官抗告の必要性を裏付ける立法事実とすることには疑問がある。さらに言えば、両決定とも、「検察官の特別抗告には理由がない」とした上で、職権判断により開始決定が取り消されているため、「検察官の特別抗告が認容された事例」ではない。
再審請求審における証拠開示の範囲について、中川氏が「証拠開示は新証拠とそれに関連する請求人の主張との関係で必要な範囲に限定されるべき。新証拠を離れて、確定判決を支える証拠との関係での類型証拠の開示は再審請求審の構造にそぐわない」との意見を述べたことに対し、筆者が「再審の実情を見ると、新証拠の証明力を判断するために開示の必要性が認められて開示された証拠が、請求人の提出した新証拠の信用性なり証明力の判断に資するというものももちろんあるが、他方で実際、開示証拠自体が新証拠として再審開始が認められたケース、また、請求前の段階でそれが開示されることによって、請求人がそれを新証拠として再審請求して認められたケース、さらにはまた、請求人が新証拠を提出しているのですけれども、実際は開示された証拠だけが明白性を認められて再審開始の確定に至ったケースというようなものが存在する。そうすると、新証拠を離れて類型証拠を広く開示するということは考えられないという点について、このような事例があることとの関係でどのようにお考えなのか」と質問したところ、中川氏は「そのような事案があるのだということは、いろいろな文献等々を拝見して認識はしているが、今回の刑事訴訟法の改正との関係で言うと、そこを入れ込むということは非常に難しい、困難ではないかと考える」と答えるにとどまった。これでは、再審請求審の構造にそぐわないという理由が冤罪の救済に優先するのを認めているようなものである。
磯谷氏は、犯罪被害当事者遺族という立場で招聘されたが、自らが被害者遺族となった事件の「犯人」とされた者が再審無罪になったわけではないので、あくまでも「そのような状況に置かれたら」という仮定に基づくコメントであることに留意すべきである。もっとも、磯谷氏は「再審請求する必要がないように、三審制の中できちんと裁いてほしいことです。再審請求に関する法案より先に、どうしたらえん罪を生まないかを考えてほしいというのが本音です。えん罪は犯罪の内容にかかわらず、あってはならないことです。これまでのえん罪事件ではどのような原因で間違ってしまったのかを振り返り、教訓にする必要があると思います」「えん罪で得する者は、本当に裁かれるはずであった真犯人だけです。被害者も、無実の罪を着せられた者も、共に被害者です」と述べており、冤罪被害があってはならないこと、冤罪被害者も犯罪被害者も同じ「被害者」であるとの立場を明確にされていた。
しかし、翌日の共同通信の報道は磯谷氏の「安易に再審ができれば終わらない裁判に人生を奪われる。司法全体の信頼が失われる」という発言だけが切り取られ[1]、あたかも冤罪被害者を敵視しているような印象を抱かせるものだった。議事録が公表されるまでにタイムラグがある中で、世論を誤導しかねない報道がされることは深刻な問題である。再審部会がリアルタイムで公開されていないことの弊害と言えよう。
最後に、髙橋氏の意見には、事実誤認と思われる箇所や文献や判例による裏付けのない独自の法解釈など、様々な問題があるが、もっとも許しがたいのは「逆えん罪」(再審請求を行った事件当事者が真犯人であるという意味と思われる)という言葉を使い、次のように述べた点である。
「日弁連が出した資料によりますと、17件のうち12件で再審開始決定が確定しています。1件はまだ係属中です。ということは、4件は不服申立てが認められています。もし不服申立権を認めなければ、この4件については逆えん罪ということになります。被害者からすれば、どう考えたらいいのでしょう。もし不服申立権を禁止してしまったら、この4件については、実は真犯人なのだけれども真犯人ではないことになってしまいましたと墓前に報告しなければいけなくなってしまう」。
この「日弁連が出した資料」とは、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の第11回会議(2024年3月15日)で日弁連の河津博史委員が提出したものである[2]。髙橋弁護士のいう、不服申立てが認められたとされた4件は、日産サニー事件、名張事件、大崎事件、福井女子中学生事件のことである。上記会議の時点で4件に含まれていた福井女子中学生事件については、7か月後の10月23日に第2次請求審において再審開始決定がされ、確定したことは周知のとおりである。
他の件についても、名張事件と大崎事件は現在新たな再審請求の準備中である。このような状況の中で、検察官の不服申立てが認められたから、再審請求を行った元被告人=真犯人であるという決めつけは、およそ弁護士にあるまじき態度と言わざるを得ない。
第3回会議のヒアリングによってもたらされた意見が、次回から始まる再審法案の検討の際に、日弁連推薦以外の委員等によってどのように「活用」されるか、今後の議論を注視すべきである。
*本著作物を、複写・印刷・転載・翻訳・頒布する場合は、こちらから事前に著作権者の許可を受けてください。
【関連記事:特集「冤罪(誤判)と再審法改正の最前線」】
・第3回「再審法改正が実りあるものになるように(連載の趣旨)——再審制度を機能強化するための3つの課題①」(田淵浩二)
・第7回「法制審議会─刑事法(再審関係)部会のリアル①──第1回(4月21日)、第2回会議(5月30日)」(鴨志田祐美)
・第9回「再審における証拠開示の理論的構造」(斎藤司)
・第10回「法制審議会─刑事法(再審関係)部会のリアル③——第4回会議(7月15日)[その1]」(鴨志田祐美)
注/用語解説 [ + ]
(2025年07月12日公開)