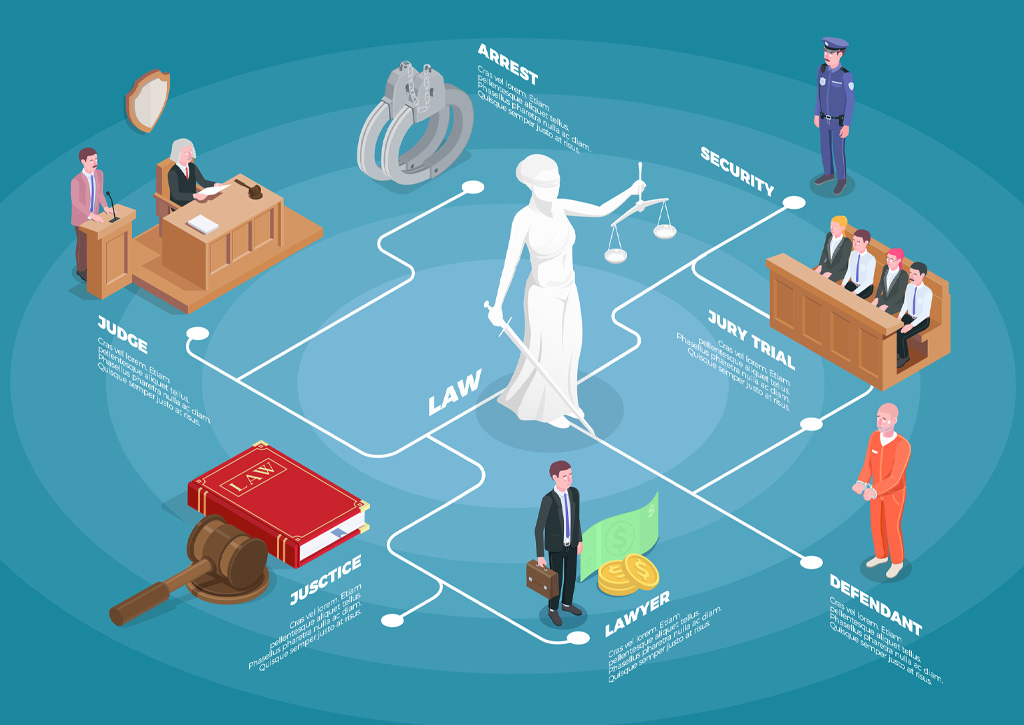
4 部会における議論の特徴と問題点
これまでの部会の議論の特徴は、被告人の逃亡を防ぎ、刑の執行を円滑に実現するために被告人、あるいは「身元引受人」に新たな義務や制裁を新たに課すことに議論が傾いていることである。弁護士の委員・幹事からは、新たな義務を課すことや罰則に対して疑問を呈する発言はあるものの、新たな制度によって現状以上に保釈が広く認められる可能性があるという観点から、あるいは被害者保護の観点から、たたき台に賛成する意見も出されている。そのため、全体としてみると、未決拘禁の極小化、あるいは無罪推定の観点というよりは、いかにして逃亡を防ぎ、身体拘束を確実なものとするか、という観点が立場の違いを超えて強く示されている印象がある。
以下、たたき台の項目に従って、部会の議論の特徴を示すこととする。ただし、紙幅との関係で、すべての項目を詳しく取り上げることができないことをお断りしておく。
⑴ 「保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防止するための方策」についての議論
まず1−1「勾留の執行停止中、保釈中の被告人に定期的な出頭、報告義務を課すこと」については、現在の制度においても出頭、報告を保釈条件に加えることができる、との指摘は[1]あったものの、弁護士の委員からも、制度化することによって、今まで保釈が許されなかった類型について保釈が出しやすくなるのではないか、という意見[2]が出され、制度を設けることについての大きな異論は出されていない。ただし、出頭、報告義務に反した場合に罰則を設けることについては、保釈の取消や保証金の没取で対応するべきで、罰則は不要とする意見が複数出されている[3]。
罰則を設けることは、1−2「身元引受人が被告人を監督して逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保する仕組み」の身元引受人の義務違反や1−3「保釈中の被告人等が正当な理由なく公判期日に出頭しない不作為などを対象とする新たな罰則を設けること」において保釈中の被告人の不出頭についても提案されている。これらの罰則についても、保釈の取消や保証金の没取で対応するべきだとの消極的意見がある[4]。ところが、1−2に関しては、弁護人が身元引受人になる場合には、裁判所が保釈を認めやすくなるとの期待感が示され、1−3についても、被告人の逃走意欲が発生する芽を早い段階で摘む意味があるとの賛成意見が出されている[5]。ここには弁護士の中で意見の対立がある。
1−4は、単純逃走罪の主体を拡大しようとする提案である。現行の刑法97条は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が逃走したことを犯罪としている。たたき台その2で示されているのは、「令状により身体拘束された者」をこの罪の主体とするという考え方である。要するに「拘禁」からの逃走ではなく、その前段階から逃走を犯罪とするというのである。これに対して、現行規定では主体に含まれていない逮捕段階の引致、留置を含めることの是非などに関して議論が行われている。
逮捕段階については、たたき台でも現行犯逮捕の場合や、緊急逮捕で逮捕状が発付されるまでの間は除かれている。これらは「令状による」身体拘束ではないからであろう。しかし、部会では、逮捕が「将来の勾留に向けたできる限り短期間の即時的な身体拘束」であるとの理解は一般的ではなく、実務上も「48時間なり72時間なりという期間を持った身体拘束と理解されて運用」されているとの指摘[6]があり、逮捕と勾留とで質的な差はないから、逃走罪の主体とすることができるという意見が出されている[7]。
筆者は、逮捕は、拘禁(勾留)の是非を判断するまでの仮の身体拘束に過ぎないと考えている。これは「一般的でない」理解かもしれない。しかし、逮捕とは、物理的な力の行使が許容される作用であるから、引致、留置中の者を事後的に逃走罪として処罰する必要があるのか、疑問に思う。罰則を設けなくても、逮捕段階で身体拘束から逃れた場合には、逮捕手続自体をやり直すことが可能だからである[8]。この点に関して「その場からぱっと逃げて、1分後とか3分後にすぐ捜査員に捕まったようなときまで新たな罪になる」とするのは広すぎるという意見も出されている[9]。施設に収容された状態である「拘禁」から逃れることと、その段階に至っていない「引致」や「留置」から逃れることを同じと考えることにはやはり疑問がある。
GPSについては、やや詳しく見ておきたい。「たたき台・その2」で1−5として、次のような「考えられる制度の枠組み」が示されている。
⑴ 裁判所は、保釈を許す場合において、必要があると認めるときは、被告人に対し、GPS端末の装着を命ずることができるものとする。
⑵ 裁判所は、⑴によりGPS端末の装着を命じる場合には、併せて、被告人に対し、一定の地域に入り、又は一定の地域から出てはならないことを命ずるものとする。
⑶ ⑴によりGPS端末の装着を命ぜられた者は、次の事項を遵守しなければならないものとする。
ア GPS端末を自己の身体から取り外さないこと〔GPS端末装着義務〕
イ GPS端末を損壊し、又は電波を遮断する等その位置測定機能を故意に失わせる行為をしないこと〔損壊等の禁止〕
ウ GPS端末の充電等、位置測定機能を維持するために必要な管理を怠らないこと〔充電等の義務〕
⑷ GPS端末の機能によって義務違反を検知し、保釈を取り消すなどした上、位置情報を活用して身柄を拘束することができる仕組みを設ける。
⑸ ⑵による命令又は⑶の義務に違反した場合の罰則を設ける[10]。
部会では、GPSの利用は必要最小限度に留めるべきであるとの意見[11]は出されているものの、導入自体に反対する意見は出されていない。議論の焦点になっているのは、義務違反が検知されたときの対応である。たたき台で示されているのは、保釈を取消すなどして身柄を拘束するという対応である。これに対して、それでは遅すぎるとして、違反がすぐに通知され、即時に介入できる制度が必要であるという意見が複数出されている[12]。
しかし、第5回会議の議論でGPS装置の具体的な運用方法についての議論が深まったとは言えないように思われる[13]。提案された「考えられる制度の枠組み」には、位置情報の取得を誰がどのような形態で行い[14]、義務違反があった場合に具体的にどのような対応を予定しているのかは書かれていない。議論の中でも、国外逃亡の可能性があるケースや、関係者との接触禁止を実効的にすべきケースにGPSが有効ではないかという期待感が示されているに過ぎない。実際にどのような技術を用い、どう運用することによってその効果が表れるのかを、諸外国の運用例も参考にしつつ検討することが必要であろう。
また、現在までの部会のGPSに関する議論は、保釈中、あるいは勾留の執行停止中の被告人を念頭において行われている。勾留の代替処分としてGPSの活用を考えるのであれば、被疑者の勾留の場合についても検討する必要がある。また、諸外国の制度においては、仮釈放の際に、あるいは社会内処遇の一環としての電子監視が先行し、それが未決拘禁の代替処分に取り入れられたという経緯が見られる[15]。そのような経験を持たないわが国において制度を全く一から創設しようとするのであれば、諸外国の制度にもっと学ぶべきであるし、身体拘束をめぐる国際的な動向にも目を配るべきである。しかし、部会の議論は身体拘束の極小化を目指す国際的な動向を考慮して行われているとは言い難い。
◎執筆者プロフィール
水谷規男(みずたに・のりお)
1962年三重県生まれ。1984年大阪大学法学部卒業。1989年一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。三重短期大学、愛知学院大学を経て、現在、大阪大学大学院高等司法研究科教授。専門=刑事法。主な著作に、『未決拘禁とその代替処分』(日本評論社、2017年)などがある。
注/用語解説 [ + ]
(2021年05月19日公開)

