
2025年9月、大麻をめぐる著名な事件が続いた。そんななか、同月9日に柴﨑大麻裁判の第5回公判(裁判長:佐々木直人)が、さいたま地方裁判所熊谷支部第401号法廷にて開かれた。本件では、大麻取締法違反(単純所持)の無罪が争われており、今回の公判では最終弁論と最終意見陳述が行われた。
大麻による意識の変容は「悪」ではない
まず、最終弁論である。丸井英弘弁護士は、前回の公判終了後から本公判に至るまでの間に、多岐にわたる資料を引用・添付した弁論要旨を準備した。資料には、これまでの公判で、証拠調べを請求したが却下されてきたものが含まれる。たとえば、アンドリュー・ワイル博士をはじめ、大麻の活用を推進する医師や研究者などが署名者に名を連ねる「カンナビスに関する世界の第一人者による共同声明」 [1]や、裁判所が大麻の所持などに懲役刑を科す立法に疑問を示した大麻取締法違反事件[2]の解説論文などがある。
弁論をするにあたり、丸井弁護士は最初に、「先入観を持たずに、良心に従って慎重に判断してほしい」と述べた。弁論要旨は1から6にわたるが、以下では、特に重要と思われる点の概要を記す(全文は記事末尾を参照)。
印象的だったのは、意識を変化させることについての議論である。丸井弁護士いわく、大麻の所持や使用が違法とされる理由は、結局のところ、「大麻による意識の変容=悪」という解釈にある。しかし、「幸福・不幸」「リラックス・興奮」「好き・嫌い」など様々なことを感じる意識の存在は、人間が人間であることの証明である(意識がなければロボットになってしまう)。ゆえに、人間として主体的に生きたいのであれば、自分の意識に対しても主体的でなければならない。
したがって、自分自身の意識を変化させたい、拡大したいと思い、そのために行動することは、人間にとっての根底的な権利であるから、意識変容の方法の一つとして(すなわち、いわゆる「多幸感」を得ることを目的に)大麻を所持・使用することは、「悪」ではないという。
争点の一つであった鑑定について丸井弁護士は、「本件植物片が、(大麻取締法にいう)大麻草(カンナビス・サティバ・エル)であるかについての科学的検討を行なっておらず、有罪であることの立証が不十分である」と述べた。
この主張の根拠は、第2回公判で行われた、鑑定人(神奈川県警察科学捜査研究所の技術職員)に対する証人尋問で明らかとなった、以下の3点である。
① 本件植物片が大麻草であるかを形態から判断する際の、基準となる標本が存在しなかった。
② 本件植物片が大麻草であるかを形態から判断する際、鑑定人は大麻草に似た剛毛を持つ植物があることを知らなかった。
③ 鑑定人は、本件植物片からTHCが検出されたと判断する際の標準品が、大麻草由来か化学合成由来かを確認していなかった。
続いて、被告人・柴﨑和哉さんの最終意見陳述である。裁判の最中、実刑のおそれという身近に迫る不利益と、自らの経験に基づく大麻に対する実感との間で揺れ動いた柴﨑さんだったが、証言台の前に進み、明瞭な声で最後の陳述を行った。
柴﨑さんの、この裁判での最終的な立場は、以下のとおりであった。
サポートしてくれている人々に迷惑や心配をかけたことは反省し、そのような状況をもたらさないようにするため、法を犯すことは二度としない。だが、何らかの新しい判断を示してもらえると信じ、これまでの立証活動に努めてきた。裁判官には、判例[3]が出された後に発表された、世界的な大麻政策の方向性や大麻の有害性に関する科学的知見を直視してほしい。
柴﨑さんは、世界情勢として、薬物政策に関する国際委員会(GCDP)等の国際機関が、薬物の単純所持や使用を罰することについて否定的な見解(“Beyond Punishment: From Criminal Justice Responses To Drug Policy Reform 2024” )を示していることなどを述べた。
科学的知見については、様々な薬物の有害性を採点した、David Nuttらによる研究に言及した。同研究では、①使用者に対する身体的害、②精神的害、③社会的害、④他者に対する身体的および精神的害、⑤社会的害の5つのグループからなる、16項目の危害基準(harm criteria)を用いて、有害性のスコアが数値化されている。合計スコアが高い順に、アルコール、ヘロイン、クラックコカイン、メタンフェタミン、コカイン、タバコ、アンフェタミンと続き、大麻は8位であった(以下、ベンゾジアゼピン、ケタミン、メタドン等12種類が続く)。
「ごめんなさい裁判」にはしたくなかった
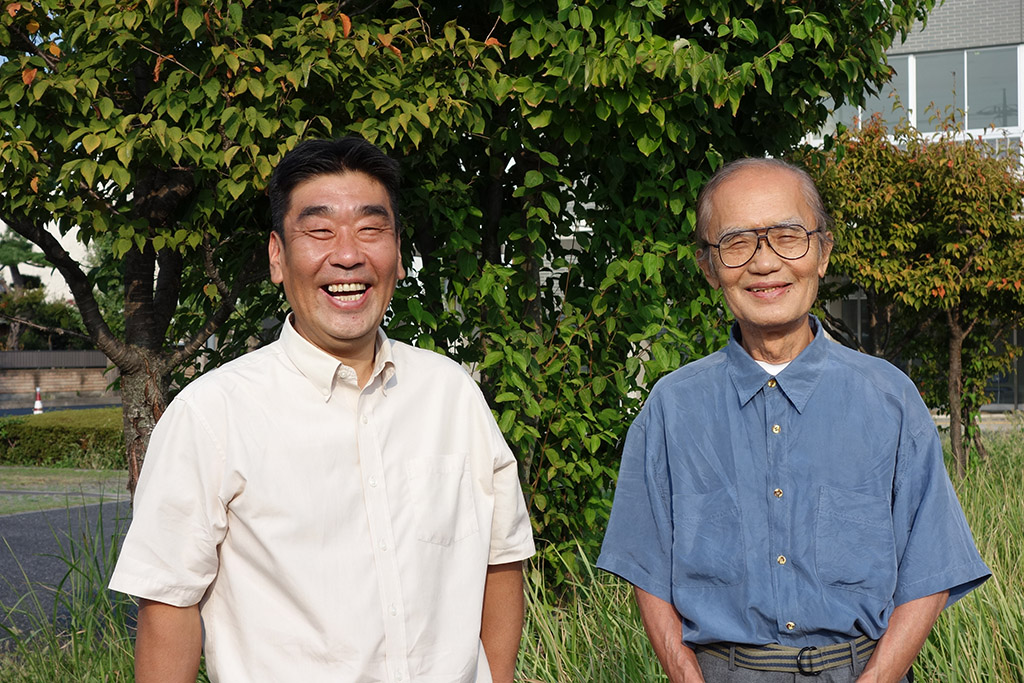
丸井弁護士の弁論は、重要な、しかし、ともすれば自覚的であることを忘れがちな、個人は「自分自身の身体と精神に対しては、主権者である」(J.S.ミル『自由論』を参照)ことを、強く再認識させてくれるものであった。
本公判を振り返って、丸井弁護士は、「これまでの公判では、弁護側請求証拠は全て却下されて、ひどいものだった。でも今回は、弁論で引用し、添付することを(裁判官に)認めてもらえた点は良かった。提出したものにすべて目を通してくれれば、大麻事犯に対する判決の流れは変わる」と述べた。
柴﨑さんは、最終意見陳述について、「検察側に『再犯に及ぶおそれが高い』などと言われているなかで最終意見を言うのは怖かった」という。だが、「ただの『ごめんなさい裁判』にはしたくなかった。その点から言えば、周囲の励ましもあって大麻についての自分の見解を言えたし、清々しい気持ちもある」と公判後の気持ちを語った。
大麻裁判の支援活動を広く行なっている長吉秀夫さんは、「意識についての主体性の話は、まさに今の大麻規制が抱える大きな問題点。これを(本公判で)言ったことにはとても意味がある。反省だけではなく、大麻規制に疑問があることも言い切ったのは、柴﨑さんの人生にとって重要なことだと思う」と本公判の意義を語った。
柴﨑大麻裁判の傍聴に、毎回来ている方は、「いかに論理的に破綻していたとしても、一度成立してしまった法律を変えることは非常に難しい。事件の当事者ではない人が関わってくれて、(その当事者は)悪くないと思ってもらうことは、(ルールを変えていくうえで)非常に重要だと思う」という(被告人自らが処罰根拠法に異議を申し立てる難しさについては、前回の公判を参照)。
柴﨑大麻裁判が、事件の当事者以外も大麻政策の現状に疑問を持つきっかけとなっていることは、柴﨑さんのお店でスタッフをしている方の言葉からうかがわれた。「近くで見ていると、柴﨑さんは多くの人から信頼されているし、危険人物ではないとわかる。でもそれは、(大麻事件の当事者に対する)一般世論とは違っていて、もどかしい。最初、大麻のことはよく知らなかったが、この裁判を通じて、今の大麻規制がいかに(当事者の声が聞き入れられず)ときの権力者に作られてきたかを感じる」。
そして嬉しいことに、今回、新たに傍聴に来てくれた方もいた。
日々、大麻所持罪や大麻施用罪の疑いで逮捕され勾留される人、有罪判決を受ける人がいる。事件の当事者ではない人にも(こそ)、今一度、「本当に処罰すべきだろうか」「本当に禁止すべきだろうか」と、立ち止まって考えてみてほしい。
次回は、判決公判となる。日時は、2025年10月14日(火)13:30〜14:00、場所はさいたま地裁熊谷支部で開かれる。
丸井弁護士がさいたま地裁熊谷支部に提出した弁論要旨は、以下から閲覧できる。弁論要旨6は、弁論要旨1、2、3の補充の要約も兼ねており、時間のない方にもぜひご覧いただきたい。
・弁論要旨1
・弁論要旨2
・弁論要旨3
・弁論要旨3の補充
・弁論要旨4(補充分含む)
・弁論要旨5
・弁論要旨6
なお、読者の便宜のため、誤字・脱字、改行、字下げおよびフォントなどの形式面について、編集部で修正を加えた。
注/用語解説 [ + ]
(2025年10月07日公開)

