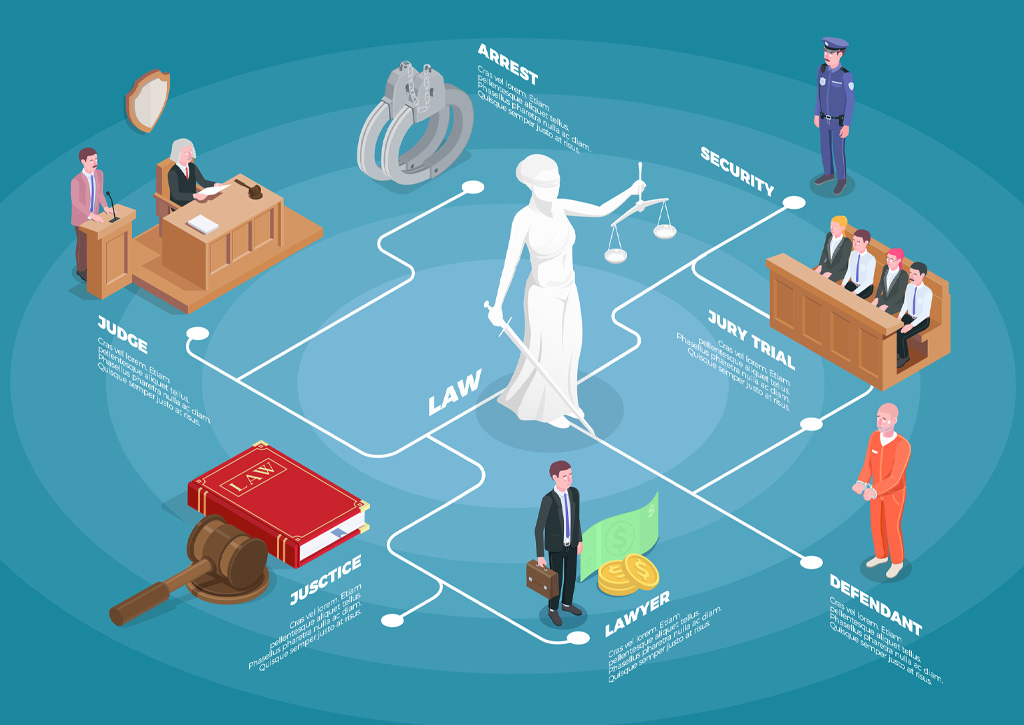
⑵ 「判決宣告後の被告人の逃亡を防止するための方策」についての議論
たたき台が取り上げている項目は、2−1「禁錮以上の実刑判決の宣告後の裁量保釈(再保釈)について、同判決の宣告前の場合と比較して、要件を厳格なものとすること」、2−2「控訴審の判決宣告期日への出頭を被告人に義務付けること」、2−3「禁錮以上の実刑判決の宣告後、被告人が現に逃亡した場合における制裁(保釈の取消し及び保証金の没取)を強化すること」、2−4「禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた者が出国により刑の執行を免れることを防止する仕組み」の4つである。
2−1についての議論では、裁量保釈の規定(刑訴法90条)との関係が議論の焦点となっている。たたき台では、①保釈されない場合の不利益が逃亡のおそれを上回るほど著しく高い場合、②禁錮以上の実刑判決の宣告後であっても、保釈された場合の逃亡のおそれの程度が著しく低い場合に限って、実刑判決言い渡し後の再保釈を認めるとする案が示されている。再保釈を制限する根拠として挙げられているのは、「禁固以上の実刑判決の宣告により一般的・類型的に逃亡のおそれが高まること」である[1]。これを考慮するとしても、裁量保釈の判断自体は刑訴法90条の規定による判断のあり方と変わらないというのが当局の説明である。
しかし、原則として保釈を認めないという規定を設けることは、90条とは異なる基準を定めることになる、との疑問が示されている[2]。現在の実務でも再保釈については慎重に審査されているという前提で考えると、たたき台が提示した2つの場合にのみ再保釈を認めるとの規定を設けることは、実務のあり方に強い影響を与えることになろう。このような新たな規定を設けることには慎重であるべきである[3]。
2−2の控訴審の判決宣告期日への出頭を義務付ける制度は、「裁判の適正を図るとか、被告人の権利の保護を図るというものではな」く、あくまでも刑の執行を確保するためであると説明されている[4]。控訴審では被告人に弁論能力が認められていないという理由で出頭を不要としながら、刑の執行確保のためという理由のみで判決宣告期日への出頭を義務付けるという考え方自体に疑問を覚えるが、部会の議論では、出頭を義務付けても被告人が出頭しなかったらどうなるか、という点に関心が寄せられている。その場合に判決の宣告ができないものとすると、被告人が判決宣告を先延ばしにするために出頭しないという問題が生じるとの危惧が表明されたりしているのである[5]。
しかし、部会でも指摘されているとおり、現在の規定の下でも、保釈条件として宣告期日への出頭を義務付け、出頭しない場合には保釈を取消して判決宣告期日を延期し、身柄を確保してから延期された期日に出頭させる対応が可能である[6]。宣告期日への出頭確保の問題は、これを踏まえて、控訴審における被告人の地位という、より大きな視点から考えるべき問題である[7]。
2−3の禁固以上の刑の言渡しの後保釈されていた被告人が逃亡した場合への対応について提案されているのは、刑訴法96条3項の規定の前倒しと逃亡した場合の保釈や勾留の執行停止の必要的取消しである。刑訴法96条3項は「刑の言渡しを受けその判決が確定した者」が執行のための呼び出しに応じないときや逃亡したときを必要的没取の対象としている。これを判決宣告後、確定前に広げようというのである。
ここで気になるのは、「刑の執行の確保という保釈保証金の機能を全うさせる」、という当局の説明である[8]。勾留は本来、裁判のための身体拘束であって、刑の執行確保のための処分ではない。逃亡したことに対する制裁として保釈保証金を没取するという考え方はあり得る。しかし、逃亡したことによって保釈や勾留の執行停止が取消された場合には、刑訴法98条による収容手続が行われ、それによって刑が確定した後の執行が容易になるという事実上の効果があるだけである。刑の執行のために勾留する、逃亡を防ぐために保釈保証金を必要的に没取する、というのは、保証金を出しているのが被告人とは限らないという実情を踏まえると、妥当とは言い難い[9]。
2−4は、実刑の言渡しを受けた者の出国を防ぐ措置を新たに設ける提案である。想定されているのは、保釈保証金の没取と出入国管理及び難民認定法の出国確認手続における留保制度を活用して、保釈取消しまたは勾留で対応することである。また、禁錮以上の実刑判決の宣告を受けた被告人について、退去強制事由があるときには、そのことを理由として勾留することを認める規定を創設することも提案されている。ここでも刑の執行確保のために勾留するという考え方が示されている。刑の執行確保を勾留の目的として認めてよいのか、を正面から問い直すことなしに、便宜的に勾留に頼ろうとすることには疑問を覚える。
部会の議論では、退去強制事由がある場合には、勾留するのではなく、裁判の進行中は在留資格(日本で裁判を受けるために滞在する権利)を認めるべきだ、との提案が行われている[10]。しかし部会の議論は、出入国管理と刑事司法との調整という問題で錯綜したものになり、議論の方向性が定まっていないと言わざるを得ない。もっとも、保釈条件として裁判所が出国を禁止していても、出国手続の際にそれが考慮されないという実情があるとすれば、出国管理の問題として、制度改正を考えるべきであろう。ゴーン事件でも出国を阻止できなかった出入国管理体制の不備が問われるべきであって、保釈に問題があったわけではない。
◎執筆者プロフィール
水谷規男(みずたに・のりお)
1962年三重県生まれ。1984年大阪大学法学部卒業。1989年一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。三重短期大学、愛知学院大学を経て、現在、大阪大学大学院高等司法研究科教授。専門=刑事法。主な著作に、『未決拘禁とその代替処分』(日本評論社、2017年)などがある。
注/用語解説 [ + ]
(2021年05月27日公開)

