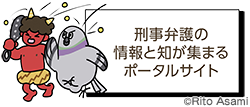2025年10月14日、さいたま地方裁判所熊谷支部第401号法廷にて、柴﨑大麻裁判がついに判決公判(裁判長:佐々木直人)を迎えた。2024年12月から約10カ月にわたり、「みだりに、……において、大麻である緑褐色葉片合計約4.255グラム及び大麻を含有する緑褐色葉片等約0.41グラムを所持した」(大麻取締法24条の2第1項違反)との公訴事実に対して、大麻所持罪の無罪を争ってきた(これまでの流れは、末尾に記載した過去の記事を参照)。
40年前の「公知の事実」
開廷すると、裁判長の指示で、被告人・柴﨑和哉さんは緊張の面持ちで証言台の前へ進んだ。裁判長は、氏名等の確認を終えると、判決とその理由を告げた(判決文は、LEX/DB25623574に収録)。
「主文 被告人を、懲役8月に処する。さいたま地方検察庁熊谷支部で保管中の大麻3袋(令和6年領第139号符号1ないし3)を没収する。」
判決理由として、丸井英弘弁護士の各主張につき、以下のとおり述べた。
まず、柴﨑さんは健康保持目的で大麻を使用するために所持していたのであり、本件行為が、大麻取締法の保護法益とされる「国民の保健衛生」の保護に反することは証明されておらず、「みだりに」所持していたとはいえない、との主張についてだ。
裁判長は、「大麻取扱者の免許を持たない被告人が健康保持目的で大麻を所持することは社会通念上正当な理由に当たらない」、保護法益についても、「大麻の薬理作用が人体に有害であることは公知の事実である」とした。そのうえで、上記丸井弁護士の主張は「独自の見解」であり採用できないと退けた。
次に、本件葉片が「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」(大麻取締法1条)であることは、鑑定において明らかになっていない、との主張についてだ。丸井弁護士は、①本件葉片が大麻草であるかを形態から判断する際、基準となる標本が存在しなかった、②鑑定人は、大麻草に似た剛毛を持つ植物があることを知らなかった、③THC検出の有無を判断する際の標準品が、大麻草由来か化学合成由来かを確認していなかった、と主張してきた(第2回公判を参照)。
裁判長は、本件大麻鑑定について以下のとおり評価した。本件鑑定人の「学識や鑑定経験は豊富であり、本件で用いられた鑑定手法や判定基準は合理的なものであって、……〔本件鑑定人による〕鑑定結果は信用することができる」。
丸井弁護士の主張に対しては、「いずれの主張も〔鑑定人〕が述べる鑑定手法に疑義を生じさせるものではなく、弁護人の指摘する事情を踏まえても前記鑑定結果に疑いは生じない」として退けた。
本件大麻鑑定に対する、上記評価には疑問が残る。裁判長は、鑑定の信用性判断につき、鑑定人の豊富な経験を挙げた。たしかに、第2回公判で行われた証人尋問にて、本件鑑定人は6,000〜7,000件の大麻鑑定を行ってきたと証言している。しかし、経験件数が多いことが、どうしてその鑑定が信用できることにつながるのだろうか。
続いて、大麻取締法は憲法違反であり無効である、本件への大麻取締法の適用は適用違憲である、との主張についてだ。
裁判長は、判例(最一小決昭60・9・10LEX/DB27803849、最一小決昭60・9・27LEX/DB25352393、最二小決平6・6・10LEX/DB25352771等)を参照しつつ、「大麻の有害性に鑑みて刑罰をもってその所持を禁止することは、国民の保健衛生上の危害防止という重要な公共の利益を保護するため必要かつ合理的な措置であって立法裁量を超えるものではない」とした。同法は憲法に違反しない、との判断だ。
なお、丸井弁護士は意見書等で、同法の立法経緯なども振り返りつつ、同法は憲法13条(幸福追求権)、14条(法の下の平等)、22条(職業選択の自由)、25条(健康で文化的な最低限度の生活)、31条(適正手続)、36条(残虐刑の禁止)に違反する旨を詳細に述べていた。しかしながら、裁判長は判決で、同法が憲法各条にいかにして反しないかを詳らかに述べることはなかった。
求刑が懲役1年のところ、量刑が8月とされたことについては、柴﨑さんの大麻に対する「依存性、親和性は明らか」だが、「今後は大麻を使用しない旨を述べている」「更生につながる支援者の存在もうかがえる」等の事情を考慮しての判断だという。
裁判長が、控訴できる旨を告げた後、本公判は終了した。告知の直後、柴﨑さんと丸井弁護士は二〜三言交わして控訴する方針を固め、同日に控訴の手続を行なった。
閉廷後の法廷には、支援者の方の「罪を犯しているとは思えません」という言葉が響いた。
すべての弁護人は、どんどん争ってほしい
判決を受けた柴﨑さんは、「非常に、残念です」と口にした。しかし、「実際に実刑判決を受けてみて、もう一段階腹を括った。大麻に対する世間のネガティブな印象を少しでも減らせるように、(これまでやってきた店舗経営やイベント運営の経験を活かして)控訴審までの間で何かしたい」と、展望を語った。
丸井弁護士は、「人を閉じ込めることは、本来なら逮捕・監禁罪になる。それなのに、憲法の議論をせずに『公知の事実』で逃げて、具体的な理由を述べずに懲役の判決を下している。いまの司法は機能不全だし、手続にかかる費用も刑の執行費用も税金が使われる。これは『国家的犯罪』だ」と、憤りを露わにした。
大藪大麻裁判で、同じく大麻所持罪の無罪を争う大藪龍二郎さんは、「憲法上の問題がいくつも指摘されているのに、具体的な議論が何も展開されていない。40年も前の判例を引用されても、どこが『公知の事実』なのか。自分もさんざん同じ思いをしてきた。(どんなに具体的に問題を指摘しても議論がなされず)卑屈な人間をつくるシステムだ」と、大麻事件に対する裁判所の態度を批判した。
また、「大麻事件を担当するすべての弁護人は、大麻取締りの根拠法についてどんどん争ってほしい」。これは、柴﨑さんと丸井弁護士の共通見解だ。傍聴に集まった支援者の方々も、首を縦に振る。
柴﨑さんいわく、処罰を受ける理由に違和感を持っていたとしても、「弁護人が、大麻取締法について争うという選択肢を示して一緒に闘ってくれる人じゃないと、被告人は何もできない。『ごめんなさい』と謝らざるをえなくなってしまう」。もちろん、当事者たる被告人に争う意向があるかどうかは重要だが、だからこそ、争う選択肢を提示できる弁護人が増えてほしいところである。
報告会では「公知の事実」に注目が集まったが、「社会通念上」正当でないという表現も印象的であった。「社会通念」とは、「社会で一般的に受け入れられている物の見方・判断」とされる。しかし、価値観が多元的な現代では、そもそもある事柄について「社会通念」が存在するのか、存在するならばその内容は何かについて、自明ではない(高橋和之ほか編『法律学小辞典〔第5版〕』(有斐閣、2016年)の「社会通念」を参照)。現行のルールありきの判断でよいのだろうか。
法制度の変革は、現行制度の問題に気づいた人たちによる、「今できること」の積み重ねだと思う。柴﨑さんの闘いを、日本の大麻政策を好転させる一歩にしたいところだ。
(お)
【柴﨑大麻裁判の動き(過去の記事)】
・第1回公判(2024年12月24日)、第2回公判(2025年3月11日)
・第3回公判(2025年5月13日)
・第4回公判(同年6月10日)
・第5回公判(同年9月9日)
・第6回公判(同年10月14日、本記事)
(2025年11月12日公開)